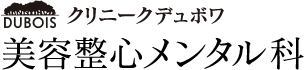思春期失調症候群
定義
思春期失調症候群とは、思春期という発達段階(ライフサイクル)の乗り越えなければならない課題をうまく消化し乗り越えることが出来ず、精神、身体に失調を来し、不登校、引きこもり、アパシ―、家庭内暴力、行為障害(非行)、摂食障害、リストカット、身体醜形障害(症)、境界性パーソナリティ障害など一連の症状を示すものを言い、私が名付けたものである。
思春期は、身体的には第二次性徴の時期で、安定した成人に成熟する過程における急激な身体の変化とホルモン代謝機能のバランスを欠いた不安定な時期であり、精神的には大人社会に参入するために自我が成長する時期で心理的にも不安定な時期になる。
この時期にうまく発達を進化できずに、つまずくと頭痛、腹痛などの心気症、うつ病のような、抑うつ感、活動性の低下、さらには「生きる意味が分からない」「自分は存在する価値がない」などと自己肯定感が持てず無力感に囚われたり、初期統合失調症のような離人症、被害念慮、被注察感などの諸症状を呈するようになる。
また不登校、引きこもり、アパシー、家庭内暴力、行為障害(非行)、あるいは摂食障害、自傷(リストカットなど)、身体醜形障害(症)などのような形で大人社会への参入から逃避したり拒絶を表出することがある。
既に思春期挫折症候群(稲村博、1982)という病名があるが、これは思春期において「学力低下、いじめ、虐待、両親の不仲(離婚)、家庭問題、恋愛の失敗、友人関係のトラブル、教師とのトラブル」など自尊心・自己愛が傷つくような挫折体験をきっかけにして、心気症状や抑うつ症状などの神経症様症状や家庭内暴力、登校拒否、家出、非行などの逸脱行動、被害念慮や集中力低下などの思考障害、無気力、無為などの意欲障害、退行などの症状を呈するものを言う。
思春期失調症候群は、そのような明確な挫折体験がなくとも思春期挫折症候群に類似した症状を呈するとした概念であり、より広範な思春期の精神失調をさすものである。
成因論
Ⅰ.自己の障害
思春期失調に陥っている若者たちの心理的な特徴は、「自分は何を感じているのか」「自分はどうしたらいいのか」「どう人とかかわればいいのか」「どの様に問題を解決すればいいのか」「問題は何なのかすら、わからない」から、さらに「生きる意味が分からない」「存在する価値がない」などの心理状態に陥っており、」コミュニケーション障害を来たしているが、一言で言えば、「自分そのものが分からない」「生き方そのものが分からなくなっている」心理状態であり、「自分で感じ、考え、自分で生きて行くこころ中心である自己が機能していない」と考える事も出来る。この状態をマスターソンは「自己の障害」と呼んだ。
この考えは、バリントの、生きる上で最も基本的なものが欠けている「基底欠損」、ブルックの摂食障害の中核症状としての「自己感覚の欠損」というような欠損モデルと言われるものに近い概念である。
これは従来の精神医学がとってきた無意識下の葛藤が神経症やパーソナリティ障害として現れるとした葛藤モデルに対する新しい捉え方である。
マスターソンの言う自己の能力は、1)主体性および感情が生き生きしてること2)自分であるという資格・権利意識が持てること3)自己の活性化、自己主張、自己を支える力があること、4)自己の活性化を認められ、自己価値を維持できること、5)苦痛な感情をなだめられること、6)自己の連続性があること、7)親密性があること、8)コミットする能力、創造性などがあげられており、これらが障害されるのが「自己の障害」である。
自己の能力は、第一に親(特に母親)との関係性の中で育まれると考えられている。
すべての原因をそこに帰すことは出来ないが(最近は見直し論も強いが)、思春期失調の母子関係で共通して見られることは、「親子関係の間合いの悪さ」である。もう一つは父性の欠如である。物理的あるいは心理的に父性が欠如していると母親が過剰対応になり、そうでなくとも過干渉で支配的であったりすると母子間の距離が近すぎることになり、一方共感的体験や反応が過小で距離が遠すぎたりすると、母親は自他の心理的な境界が不鮮明になり混乱するし、子供は自我境界が曖昧になる。
これは、子供の気持ちを感じ取ること、想像することよりも親の側の不安や願望から子どものこころを決めつけてしまう関係性ともいえる。又何より子どもが自分感覚を育てにくく、自分を語りづらいコミュニケーションになることが多い。このことが自分を感じ取る力を弱らせ、自分を語る力を低下させ、一方的に相手の気持ちを読み過ぎ、傷つきやすい傾向に関与していくと思われる。
長期化する不登校・引きこもりでは、このような親子関係が大きな要因になっている可能性が高いとされている。
クリューガーによれば、母親の共感的な同調作用が不十分であったり、自他を明確の区別する自我境界の体験が不十分であると、他者の延長ではない確固たる身体感覚、自己の心理的イメージを体験できにくく、また子どもが母親へのアタッチメント愛着が不安定であると、身体への満足度は低くくなると言われ、正しい自分のボディイメージ、セルフイメージを獲得することが困難になるといわれる。
ボディイメージの障害は摂食障害や身体醜形障害(症)として現れるが、これは母親に満たされなかった適切な関係性や同調性のために、果てしない愛と受容を求めて病的なネガティブなボディイメージを抱きやすくなるためと説明することが出来る。
2.発達段階(ライフサイクル)のつまずき
思春期失調症を力動精神医学で説明するには、思春期失調に関わる要因として、エリクソンの3つのライフサイクルの課題を考えると理解しやすい。
1) はライフサイクルの乳児期(0歳から2歳)の基本的信頼の獲得の失敗で、バリントの基底欠損にあたるもの、2)は幼児期、(2歳から4歳頃)の自律性、自主性、セルフコントロールの力の獲得失敗、これはマーラーの分離個体化の失敗に相当するもの、。3)は思春期(12歳から22歳)のアイデンディティ確立の不首尾である。
3つの要因は、独立したものではなく、前段階を経て連続的に達成されるものであるから理論的には1)の欠損モデルを出発点におけば、2)、3)を派生するa1)+2)+3)のモデル、2)から始まるb2)+3)のモデル,3)から始まるc3)の3種類になるが、実際にはそれらを厳密に区別するのは難しい。
あえていえば、aでは、基底欠損がベースにあって、幼児期に部分対象関係から全体対象関係を築けず妄想分裂ポジションにあって思春期に「生きる意味が分からない」など実存的な悩みが根底にあるような境界性パーソナリティ障害となる、あるいは自己肯定が出来ない不安定さが身体醜形障害(症)のように身体の表現として現れたようなモデルである。
bは自律性、分離個体化の失敗が強く現れ、見捨てられ不安、独立願望と依存願望の葛藤から境界性パーソナリティ障害、行為障害などとして出やすいモデルである。cは思春期に入って、私的自己意識と公的自己意識のギャップに悩むような思春期特有の悩みから始まる身体醜形障害(症)を示すモデルということが出来よう。
つまり同じ障害でも、必ずしも同じモデルから発症するとはかぎらないと思える。
3つのライフサイクルを見てみると、
Ⅰ)乳児期(0~2歳)は、母に愛されることで、人を信じ、自分を信じられるという「基本的信頼」を獲得し、自尊心が生まれる時期である。
人生の最初の時期で、人の人生を決定づけるという程にもっとも大事な、「基本的信頼」を獲得する時期に当る。
基本的信頼basic trust とは、人を信じることが出来るようになることで、同時に自分を信じることが出来るようになることを言い、自分を信じることが出来るようになると、生きて行く自信がつき、自分の存在に誇りが持てるようになり、自尊心が生まれる。
この根本的な意識が持てないと、自我を主張し人並に普通に生きて行くことが難しくなるので、基本的信頼が持てない状態をバリントは「基底欠損」と呼んで、生きる上で基本的な基底が足りない欠損状態とした。
基本的信頼がどのように形成されるかというと、これは一にも二にも母親の無条件の愛情の賜物であり、母親の子供に対する「没頭愛」があってこそ、子供が母親に全幅の信頼を持って依存し「愛着」を持つことが出来る。この関係性から基本的信頼は醸成される。
これは、人の成長には母親、あるいは母親に代わる人が必須であるということを意味している。
2) 幼児期(2~4歳)は、愛されながら自信をはぐくみ「自律性」を身につける時期である。
2歳から4歳ころに乗り越えなければならない危機的な主題は「自律性」の獲得になる。
自律とは自分を律すること、自らをコントロールすることである。
自律性は、乳幼児期に自信が育っていないと獲得できない。そして自信は、前述したように乳児期に基本的信頼が獲得できていないと生まれないのであり、自律性は基本的信頼の延長上にあることになる。
つまり、乳児期に自信が持てなかった子にセルフコントロールを教えること、つまり自律性を身に着けさせることは極めて困難なことになるのである。
例えば、躾というような、外からの圧力を受け入れ、自分の衝動を統制し自分のなかで折り合いをつけ、どう振る舞うか決めて行く枠組みを作ることが、自律性を築く中心的な仕事になる。つまり、外からの要求と自分の内からの要求とがバランスと取ることであるが、うまくいかないと、「うまくやれていない」という、外からの要求に応えられない恥の意識が生まれ、また「自分はいったいどうなっているのか?」と言った自分に対する疑惑を持つようになり、生きて行くことに苦痛が生じてくる。
幼児期は、「ボク スル」の一言から始まる。すべてを母親に頼り、親まかせにしていたものが、自分でやろうとする。母親の言う通りにしなくなる。ぐずったり、駄々をこねたり、口答えをしたり、憎まれ口をたたいたりする。
これが、第一反抗期と呼ばれるものであり、3つ4つの憎まれ口は自律の為の行動化(acting out)とみられ、この時期の子供の行動は、母親をイライラさせたり、不安にさせたりするが(第一反抗期)、母親が行動化に伴う危険を見守り、母親自身の不安を 乗り越えて育児に当ることが、子供の自律を達成させる鍵になる。
この発達過程をマーラーは、子供は生後、自閉期、共生期、分化期、練習期、再接近期、を経て、およそ3年間をかけて、分離個体化を成し遂げる過程とし、乳児は生物的な生を受けた後に、ここで初めて「心理的な誕生」(サイコロジカルバース)をすると言っている。
分離個体化し独立した自我を形成するためにも、安全基地としての母親に愛着しなければならないし、そのような依存対象が無いと、分離不安、見捨てられ不安が残り、依存と独立のジレンマから個体化の失敗に陥り、独立した自我が出来ないことになる。
この第一反抗期を示さず自律を済ませないと思春期の自立(親や世間や今までの自分自身への反抗である「第二反抗期」を通して自己を確立する)に際してアイデンディティの確立が困難となり、思春期に、不登校、家庭内暴力、リストカット、摂食障害等の思春期失調症状を招くことになる。第一反抗期(分離個体化)を思春期の第二反抗期(第二の分離個体化とも言う)に持越し、一度にやらなければならないために問題が大きくなるのである。
自律しようとすると、自分の判断が必要となる。親の判断と異なる判断をしなければならない。最初は判断というより、「母親はこうしろと言ったが、自分はこちらの方が面白そうだ」という衝動である。
フロイトは衝動を抑える働きとして「超自我」の概念を仮定し、超自我は幼児期に形成され始めるとしている。超自我は社会的良心であり、社会的秩序であるが、まず家庭内の秩序をモデルとして生まれてくる。家庭内に秩序が無かったり、家庭内のモデルが社会の秩序と大きく食い違っていると子供の超自我は混乱を起こし、超自我の形成不全を起こす。
子供の超自我モデルの最初は父親であり、子供は母親をとおしての父親イメージ像を作るので、母親が、父親イメージとして「尊敬と畏怖」「寛容と厳格」の両方を示すことが必要だが、子どもはこの二律背反的なものをバランスをとって感じることで、自分の衝動の統御と解放のバランスを学ぶことが出来る。
従って父親の不在は、超自我形成におおきなひずみを残し、自律の阻害要因になる。
具体例を見ると、幼稚園では、協調出来ていい子であるが、家では駄々っ子で手のかかる子供が、基本的信頼を獲得し自律性を持っている子供に相当する。幼稚園でルールを守れない子は、自律性が得られていないのであり、それは、その前の段階で基本的信頼を感じる相手が持てなかったこと意味し、従って躾をするのは簡単なことではない。
躾とは子供に大人の文化を教えて行くことであるが、言葉が理解できるようになる頃に、例えば、手ではなくスプーンで食べよう、おしっこはトイレでしようなどと教え、何をするか、しないかは、子供が考え、選べるようにするのが躾であり、自律性である。教えたら待つことで自律性は育っていく。
また、自律は対人関係の基盤でもある。
サリヴァンによれば、人間は人との関係によって人間になる。他者があるから自己がある。他者の存在をしっかり実感し、他者を認めることが、その後の社会的人格を形成する基盤になると言い、自律とは他者と調和がとれることを意味し、そうすることで、対人関係を作ることが出来るようになる、としています。
色々な研究によれば、いじめっ子は、親子関係に問題がある子に多いという結果が出ている。母親を信じることが出来、依存出来、親子で喜びや悲しみを共有できるコミュニケーション(共調関係)が取れれば、いじめっ子になる確率は低いとされる。
また将来、不登校、家庭内暴力、リストカットなど問題行動、適応障害などの症状は、乳幼時期に基本的信頼と共感性と自律性が獲得できていない場合になる可能性が高いと言われている。
3)思春期青年期(13から22歳)は仲間を鏡にして自分を見出しアイデンディティの確立を図る時期である。
この期を青年前期(13から118歳)後期(18から22歳)に分け、前期をさらに思春期前半(13から15歳)、思春期後半(16から18歳)に分ける考えもある。。
思春期青年期は、個人的な関係世界(家族的なパーソナルな共同体)から個人性を離れた関係の世界(社会的なインパーソナルな共同体)に歩み寄り参入していく為の準備期間であると考えることが出来る。エリクソンによれば、アイデンディティ(自我同一性)の確立が課題となる時期になる。
つまり思春期は「自分はこういう人間なんだということを知ること」であり、「自分がわかる、自分自身を客観的な目で見られるということ」、「自分が他人にどう見られているかを意識すること」、つまり公的自己意識が高まって来るのである。
学童期までは何事も主観的に考え、人が自分をどう見るなんて気にしないのが普通であり、自分は、自分が考えるイメージ通りの人間だと思っている。それが自分は思った通りの人間ではないと気が付きだし、人に言われて客観的に自分が見えてくるようになってくる。
友人など周りの反応を見ながら自己認識、自己洞察が出来るようになってくる。
思春期になると、不特定の友人の中から価値観や主義、信条の合う仲間や親友を作り出し、その仲間や尊敬出来る先生との関係を自分を映す鏡とし、自分がどのような人間かを見出していくようになり、自分の価値、能力、長所、逆に欠点、短所、弱点を知っていくことで自分の適正が自覚されるようになり自分の社会的役割が見えてくる。そうゆう活動を通して自分を見出していき、アイデンディティが固まってくるのである。
その過程で親離れをするが、それは親から完全に離脱するのではなく、距離が遠くはなるが適切な距離を保つことが大切であり、親との距離を適度に取って、仲間たちの付き合いのなかで自分を見出していくのが健全な成長である。この過程が無いと不安定なまま20代に入ってしまう。
別の言い方をすれば、学童期までのテーマとして、学校の先生とか、家族の周囲の人たちを理想の人物として同一化し、模倣していたものが、その人の欠点や、その人と違う自分に気付くようになり、理想と失望のプロセスを通して、本当の「自分とは何者か」「自分は何をやりたいか」が見えてくることでもある。他人の影響から脱して自分が自分の主人公になっていくということ。これを同一化から同一性へのプロセスというが、これは、自分で自分を作っていこうとする心の動きであり、決定したことの責任は自分で負うという孤独を味わうことを意味し、多くのエネルギーを必要とする。このプロセスの中で、「自分が何であるか」「自分の社会の中での位置づけ」「思想的信念や価値観」を獲得していく。
この過程で、孤独感に耐えられない人は、決定のプロセスを人に任せたり、人の言いなりになって回避したり、決定を先に延ばし逃げてしまう。決定のプロセスから逃げ出すということは、自分から逃げだすことと同じだから、自分をますますわからなくなってしまう。これをアイデンディティの拡散、混乱という。
そのような場合は、アパシーやモラトリアム、引きこもり、ニートになる可能性が出てくる。しかしこれらは、本当は思春期青年期だけの躓きというより、乳幼児期の愛着関係の形成失敗、児童学童期の友達と十分交流出来なかったことなどが原因にあることが多い。
さらには、アイデンディティ確立を困難にしている要因はもっと根源的な所にあるのではないかと私は考えている。
思春期失調症候群に入る引きこもり・不登校、庭内暴力、摂食障害、境界性パーソナリティ障害、身体醜形障害(症)などの病理に親、特に母親との関係性が大きく関与している、と述べてきたが、本当にそれだけで論じられて良いのだろうかという疑問がある。
一時期、子供の様々な病的な状態の原因が母親にあるとして、母親をあたかも病原菌とするような「母原病」と言う言い方が流行ったが、親がすべての原因とする論じ方は不十分である。確かに親の養育態度からの影響があることは間違いないだろうが、現在では、親の関与が一義的な原因というより、家族間にある様々な問題は、多くの家族メンバーが抱えている問題でもあり複合的な要因が関与しているものであり、家族全体の文脈の問題として捉えるべきだという方向に変わってきている。
母親も家族全体の文脈の中でもがいていることが多く、一人悪者にすべきでないことは当然のことである。
一方で、幼児期の親の養育態度が思春期以降の子どもの病理や問題行動に直接影響を与えるという確たる根拠を示した論文はないとし、むしろ仲間の存在があれば、他者と共に生きようとする素晴らしい力が人間には生得的にあることを、例を挙げてJ.R.ハリスは言っている。
「健全な心に必要なのは、親なのか、仲間なのか、それとも生得的な何かがあるのか」という議論には決着はついていない。
アイデンディティ確立は何故難しいか?その根源的な理由
思春期前半(中学生)は、自分は他者にどう見られているかを気にしながら、自分を客観視しながら両親から離脱していく時期である、同時に性欲に目覚め自我を不安定にしながらも「自分が何者なのか」というアイデンディティ探しを始める。思春期後半(高校生)では異性を愛すること、性の役割を知り、社会的な役割としてのアイデンディティに考えが及ぶようになる。青年後期(大学生)ではアイデンディティが心理生物学的なものから、心理社会的な要因が増し、自立し始めた自我とパーソナリティの総決算を行う。自分はこの世の中で何をすべきか、何が貢献できるかを問い、何のために生きて行くかという実存的な自己意識が形成される。これをエリクソンはアイデンディティ(自己同一性)という概念でまとめた。
近年はアイデンディティの確立が困難になり、モラトリアム時代とも言われるが、それは基本的信頼・自律・自主性・勤勉性と言うライフサイクルの課題克服という問題だけではなく、もっと根源的な要因が顕著になってきた為ではないかと考える。ここで私見を述べようと思う。
こころは本質的に不自由なもの
人のこころ(精神現象)は、一人ひとりの個体の脳の内部で生起している現象でありながら、その個体の外に大きな社会的・共同的な広がりを持った現象として存在している。
私が赤いとみているバラは、他人もまず間違いなく赤いと言う。めいめいの脳内で起きている現象なのに、個体を超えて共有可能になっている。
人間は個体の持つ生理的な感覚知覚機能のまま世界をとらえるのではなく、絶えず「意味」や「関係性」の相で世界をとらえ直して、それによって個体の認識世界を社会的に他人と共有可能なものにしていく。めいめいの脳内で生起している現象なのに他人と共有可能になっている。この共同性が心の働きの特性である。
人間の心の働きは高度の共同性を持っており、精神発達とは、この共同性の獲得のプロセスに他ならない。
「こころ」は最初は外にある。赤ちゃんの心の世界は赤ちゃんの外、つまりその子を取り巻く大人たちの内にある。しかし大人たちは、最初から自分たちと同じように「心」のある存在としてかかわっていくことによって、子供の内側にも次第に大人たちのそれと同型の「心」の世界が形成されていく。
「心」は植物のように、自生的に成長、成熟したり、自分一人で恣意的に作りあげたりは出来ないものであり、他人との関係性によってのみ存在し得る。(野生のエルザは心が持てない)
人間の精神機能は、それぞれの個体の脳に属しながらも、脳の外の社会的共同性を持った現象として初めて存在する。この根本的な矛盾が、心が不自由である根元的な原因であろう。
こころとは、もともと不自由さを本質としている、健康な状態とは「心」が自由な状態ではなく、その不自由さにそれなりに折り合いがついている状態をいう。
こころが病むとは何か?自らの「こころ」の不自由さと折り合いがつかなくなった状態といえる。
人は依存して生きている
人間のこころの働きの共同性は日常レベルでは、自分以外の他人との関係に絶えず心を働かせながら精神生活を営むという形をとっている。人間は複雑高度な相互依存的な生存様式を発達させてきたので、すでに心の仕組みとして他人との関係を生きざるを得ない存在となっている。私たちの心にはいつも他人がいて、精神生活とは他人との関係抜きには営まれることは不可能になっている。
前述したようにサリヴァンは「人間は人との関係によって人になる」と言った。
人間とは他人無しでは生きられない、人間とは周りの依存性を生きる存在であるから、「依存性」を他人から基本的に保障されるかどうかは、社会的に存在できるか、に関わる重大事であり、自分は他人との関係において、安全性を脅かされないか、排除されないか、承認を奪われないかと言った不安が常にある。そのために「安全」「受容」「承認」があって初めて安心して生きて行くことが出来る。
生まれたばかりの赤ん坊は全く無力な、全く依存的な存在であり、自立するまでに随分と時間がかる。それが人間の成長の特徴であり、そこに人間の依存性の根源がある。その依存性が養育者によって十分護られて、安全が受け入れられ、存在が承認され、養育的な関わりを受けるところから個人的共同性の世界との関係が始まる。これが精神発達の出発点で、依存性にこそ心の発達の最初の核がある。
こころの形成つまり精神発達とは、認識(理解)と関係性(社会性)の両面で発達するが、一個の個体として生まれ落ちた赤ん坊が、養育者への依存に始まって、人々が互いに依存し合う共同性の世界、つまり個人的共同体から社会的共同体に次第に歩み寄っていく過程に他ならない。
依存を本質とする我々にとって、関係における安全や受容や承認のいかんは共同性を生きることに関わる死活問題であり続けるのである。
不承認と支配される恐怖
ところが、私達はこうした重層的で高度な共同世界を作り上げ、そこで依存し合って初めて生存を可能にしながらも、一方ではこうした共同性を不自由なもの、制約的なもの、支配的なもの、行き難いのとする違和の感覚・意識を持っている。これは、矛盾した非合理的な心の構造であるが、この矛盾は私たちが共同的な存在でありつつ、一人一人が個体の存在であるところからきているのであろう。
この共同性と個体性との矛盾において、共同性(共同体依存的)に生きる中で、私たちは誰しも共同世界から拒絶される(依存を断たれる)ことへの強い恐れを持つと同時に逆に共同世界に支配され,呑み込まれる(支配される)事への恐れも抱いている。
貌の見えない大きな共同性がはらむ底知れなさ、それに対する漠たる恐れと、その共同性の中で自分は真に安全なのか、という恐れがある。
近代以前の伝統社会における人々の共同意識は、地縁血縁的な共同体世界にあり、個人的な共同世界と非個人的(社会的)な共同世界はまだ溶け合っており地続きなものであったが、近代社会になって、両者がはっきり区分され、非個人的(社会的)な巨大な共同性社会が個々人の上に覆いかぶさってきた。人々は極めて高度で抽象性の高い共同世界(国家とか世界とか)を生きるようになると、それと平行して対称形をなすように「個人」という意識(近代自我意識)をより強く持って生きるようになった。
アイデンディティの確立が必要
それにもかかわらず、私たちは、生存のためには社会的な共同体に依存せざるをえないので、依存を断ち切られる、あるいは逆に支配されるのではないかという不安に打ち勝って社会的共同体に参入しなければならないが、そのためにはより明確なアイデンディティを確立して強い自我を形成して参入するしかないのである。アイデンディティの確立は、より困難になったのである。
アイデンディティが確立出来ずに自我が脆弱であると、社会的な共同体への参入を忌避し、不登校、引きこもり、アパシー、モラトリアムやニートになって自己防衛をする。あるいは摂食障害、自傷、行為障害(非行)、身体醜形障害(症)の形で参入拒否を合理化しようとするのではないかと私は考えている。
病に至る方程式
ところで人が病的な状態になるのを要素還元的に見るとどうなるだろうか。
近代医学は細菌医学を中心に科学性と臨床性を確立してきた。そこでは「症状―原因菌の同定―診断―抗生剤の選択」というアルゴリズムが組まれた。その中で進行麻痺は梅毒スピロヘータの脳感染であると野口英世が突き止め、「狂気」の一つを近代医学が克服した幸運な例となった。
結核という感染症では、多くの人は結核菌に感染しているのに実際に発病するのはほんの一部である。むしろ免疫力とか栄養状態とかストレスによって発病が決まるとも言え、結核菌は結核にとっての必要条件でしかない。-物事は複雑に絡んだ関係の網の目からなっていて、網の目のどの結び目を「原因」とみなすかは、ある意味では任意であり、病気、精神失調も同じで、何かある特定の「原因」に還元して説明するのは無理がある。多くの事象がそうであるように、発病の要因も複雑系なのである。
しかし滝川は、ある仮説で「病気、精神失調というもの」を単純化して説明することは出来るとして、次のような方程式で表わした。
P×C×I=D
Pはパーソナリティ
Cは環境
Iは出来事
Dは精神状態、(病気あるいは精神失調も示す)
精神状態とはP,C,Iの三つの要素の関数で表される。
私達は、それぞれが持ち前のパーソナリティを持って、与えられた環境の中で、様々な出来事にぶつかり合いながら生きている存在である。P、C、Iが全体としてそれなりに折り合いがついており、ぶつかる出来事を、その都度解決しながら生きておれる状態を精神的に健康な状態と呼ぶことが出来る。他方、折り合いがつかなかったり、解決に大きく失敗すれば、それが精神失調になる。精神失調も同じ様にP,C,Iの関数になる。
環境Cは社会・心理的なメンタルな環境と身体的な環境の二つの要素の相関と考えれば、C=Cm×Cphとなる。Cmは・心理社会な精神的環境、Cphは身体的(脳も含む)な環境を意味する。
同じパーソナリティの人でも失調する人もしない人もいる、同じ環境に置かれても失調する人もしない人もいる、同じ出来事を体験しても失調する人もしない人もいるという違いは、失調するかどうかは全体の関数として決まるからである。ある一つの原因に還元できないのは、この様な全体性に依って決まるからである。病気や失調がどんな構造を持つかは、3要素の中のどれに比重がかかっているかの配分によって決まる。診断とはその比重の判断のことである。
なんと言ってもあのパーソナリティ(P)では行き難かろうとなれば「パーソナリティ障害」、あんな大きな出来事(I)に遭遇すれば傷つくだろうとなれば「PTSD」,社会心理的な環境(Cm)の問題が大きかったと判断されれば「神経症」、身体的環境(Cph)に決定的な問題があるとすれば、「外因性精神障害」となる。内因性精神障害は、P、C、Iのどこに比重があるか分からない失調であるが、木村敏が統合失調症を「間の病」としていた喩をとるなら、PCIの間とする事も出来、×の所に比重があるということもできる。
私の治療論
こころの失調とは、P,Cm,Cph,Iの各々が、相互にポイティブにもネガティブ にも影響しあい相互作用した結果としてのDであり、さらにはDもがP,C,Iにフィードバックして影響するという複雑系を形成している。
しかもこの複雑系を絶妙にバランスを保チ健康を維持するためには、宇宙のバランスを保つのと同様に、全体性を自律的に統合するバランス機能があるとしか思えないのである。私はそれを「自律統合性機能AIF」とした仮説を提案している。この機能が人のホメオスターシス(恒常性)、レジリアンス(坑病性)の中心的役割を果たすものとしている。
治療は,P、Cm、Cph、Iの各々に働きかけ、バランス、折り合いの回復を図ることであり、精神医学的には、P,Cm,Cph,Iの動かせるところから動かすということになる。
Pで問題になるのはパーソナリティ障害である。パーソナリティを診断してその改善をはかるようなカウンセリングをする。
Cに関しては、私は自身の自律統合性機能理論で心身は一体であるとしているが、これは古くからの心身一如とも言われる東洋思想の根幹でもあるが、CmとCphとの関係に当てはめて考えると、Cm(心理社会的な精神環境)とCph(身体的な環境)は相互に強く影響しあって一体化していることを意味する。
それらは交感神経と副交感神経という自律神経で統合され影響しあっている。
こころを強くすることと身体を強くすることは、自律神経を介して相乗的に働く。
人はストレス下にあると交感神経が刺激され、防衛的に逃走か闘争か(flight or fight)の感情になり、身体的には血管が収縮し血圧が上がり、また外傷による細菌感染に備えて、白血球の顆粒球が増える。その状態では、相対的にリンパ球が減り免疫力は低下する。
同時に増え過ぎた顆粒球は破壊され活性酸素が産生される。活性酸素は組織を破壊するので、組織の再生増殖が図られ、その際原型がん遺伝子ががん遺伝子に変異する確率が上がりガンが発症しやすくなる。
ストレスで交感神経優位になると、リンパ球、すなわち免疫細胞が減少するので、免疫力が下がり、何もガンばかりではなく、あらゆる病気にかかりやすくなる。また精神面では、元気が出て闘争的になるが、これが続くとイライラして怒りっぽくなり、怒り、不安、怯え、恨み、傲慢、軽蔑、罪悪感などネガティヴ感情になる。
逆に精神的にポジティブな感情、感情をもつようにすれば副交感神経優位になり、身体的には免疫力が上がり健康は維持される。あるいは身体的に免疫力を上げるようにすれば、ポジティヴな感情に、プジティヴな思考をするようになる。そのポジティヴ思考がまた副交感神経優位を進め、免疫力を上げるという好循環に入って行く。
ポジティブな気持ちにするには、私の自律統合性機能主義を基に、ポジティブ心理学と解決志向型精神療法を応用した独自の心理精神療法として、マインドフルネスレジリエンス療法MBRTを行って行く。
身体的免疫力を上げるには、基本的には体をいたわり養生することであるが、①玄米食の和食中心の食事療法、②ゆったりと心と体を癒す、体温+4℃の入浴で体温を上げる。③副交感神経を刺激するように、息をゆっくり吐き出す深呼吸④体操⑤笑うこと⑥睡眠などがあり、私はそれをレジリエン生活・食事療法としてまとめている。
これらはヨーガの思想を基本とした中村天風の「観念要素の更改」「神経系統の調整」「積極的観念の養生」で示されてていることに共通することも多い。結局のところは心身一如、ポジティヴ思考と自律神経のバランスをとる、免疫力を高め副交感神経優位にして心穏やかにするということでは共通しているようである。
Iは、出来事で、多くがストレス要因になるが、生きていくうえで避けられないことである。ストレスの本質は人間関係であることが多いが、これをストレスにならないようにするには、「こうあるべきだ」だと一方的に決めつけるのでは無く、相手の尊厳を認めて、自分自身が変わる方がより簡単で賢明な生き方と言えると思う。
「こころの健康度の差」は「生きかたの差」であり、「生き方は心の持ち方」で決まる。
生き方、心の持ち方は自律統合性機能の中のこころが自律神経を介して身体的健康と密接に繋がっている。
自律神経は自然環境(季節、気圧、太陽光の強さ、気温、潮の満ち引きなど)によって大きく影響を受けることでも、人間は宇宙の自然の摂理(自律統合性)の中で生きていることは明らかである。
交感神経は、昼間の活動的な体調を調整しているが、交感神経優位の感情は、危機的状況に対応し生き抜く意味でも基本的に「ネガティヴ感情である。怒りは闘争心を煽り、恐れは逃走行動に結び付く。それ故、人の基本的感情は、危機的状況に対応することが優先されるためか多くがネガティブ感情である。
基本感情は、怒り、嫌悪、恐怖、悲しみ、驚き、喜びの6種とされるが、5までがネガティヴ感情であり、他には軽蔑、罪悪感、羞恥心などがある。
副交感神経は夜間の穏やかな休息する体調の調整をし、気持ちをゆったりと落ち着いたリラックスした状態にする。強すぎると、細かいことにくよくよする、やる気が起きない、疲れやすいなどの感情を招く。
ポジティブ感情は、感謝、喜び、安堵、受容、謙虚さ、愛しみ、希望、予期、興味などである。
ポジティブ感情は自律神経を介して副交感神経優位に導くから、リンパ球が増えて免疫が強くなり病気にかかりにくくなる。これは逆に免疫力が強くなると、心もポジティヴになり、安定した状態になることを意味する。また活性酸素が減ると顆粒球が減りリンパ球が増え免疫力が増し、感情は安定しポジティブになる事になる。
生き方、心の持ち方をポジティヴにすること、また生活習慣を改め活性酸素を減らし免疫力を高めることが生き方、心の持ち方を変えストレスフルな出来事に対する抵抗性、あるいは回復力(レジリアンス)を強めることになる。
量子論は物質は素粒子の振動であると言い,その物質波をシュレディンガーの波動法定式で表した。私は心も振動であるとして「精神波」の存在を予言し、身体(物質)と心は波動の干渉によって影響しあい、その共振状態が健康であるとし、さらに、こころと身体、自然、宇宙を自律的に統合する超越的な力の存在として自律統合性機能を考えた。この自律統合性主義が、古来からある心身一体、心身一如に対する私の説明であるが、それは量子論、科学哲学、ユング心理学、免疫学を始め現代医学の知見から導き出したものであり、私の精神医学の基盤にもなっているものである。
私の理論では、身体波と精神波の共振が心身相関であるとするから、それには身体的な恒常性の強化をはかることが精神的なレジリアンスを強化することに繋がる。それには、まず免疫機能を強化することが大事であり、それによって精神的なレジリアンスの強化が図られ精神の失調も回復させることが出来ると考える。また、当然のことながら、自我を強化することも重要ではあるが、それは「悟る」「解脱する」に近い極めて宗教的な回路であるから、万人には困難なみちである。健康的な精神生活とは、普通にはP、C、Iの「折り合いをつける」ことであり、崩れたP、C、Iのどれかの要素を変えることで可能になる。Pであれば、自分のパーソナリティを知り、対人関係の在り方を修正することで、Cmであれば、ものの見方、感じ方、こころの持ち方、振る舞いの仕方を変えることで、Cphであれば、身体的な免疫力をつけることで改善できる。
以上のような考えを基本において私は、実際的にはマインドフルネスレジリエント療法とレジリエント生活・食事療法を行っており、不登校・ひきこもり、家庭内暴力、リストカット、行為障害、摂食障害、身体醜形障害(症)など思春期失調障害の治療を行っている
エリクソンのライフサイクルの詳細は
研究室の「エリクソンライフサイクル①」
研究室の「エリクソンライフサイクル②」
研究室の「エリクソンライフサイクル③」
研究室の「エリクソンライフサイクル④」
研究室の「エリクソンライフサイクル⑤」
研究室の「エリクソンライフサイクル⑥」
参照図書
中嶋英雄「ほんとうに美しくなるための医学」2015、アートデイ出版
滝川一廣「こころの本質とは何か」2004、ちくま新書
鍋田泰孝「変わりゆく思春期の心理と病理」2007、日本評論社