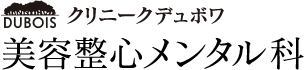『クラゲになりたい』前篇 ―身体醜形症少女の想い
○○高校3年 女子18歳
「クラゲはね、全身で呼吸をするんだよ」
と少女は言った。涼しげな、心地よい彼女の声は、鋭利な刃のごとく私の脳髄に言葉を一言一句刻んでいった。私はあまり信心深い方ではないし、非現実的なことは一切信じない。それでも、そう教えてくれた少女にもう一度会いたいと、あらゆるものに祈らずにはいられなかった。
*
美しいものは素晴らしい。美しい、ただそれだけで我々は存在を十二分に肯定し、賞賛し、愛し、感動する。幼少の頃から美しいものが大好きだった。細かい模様があしらわれた本の表紙、鮮やかな草花が描かれたティーカップ、いくつもの歯車が精巧に組み合わさってできたオルゴール、まばたきをするたびに色調を変える夕焼け。こうして美しいものに囲まれていれば、白分も同じように美しくなれると信じていた過去の夢見がちな自分が懐かしい。私はいつの間にか美しいということに固執し、それ以外を否定するようになっていた。
あの頃から随分と時は経ち、私はすでに二度目の高校の夏を迎えた。出会いもなければときめきも新鮮味も楽しさもない、それにもかかわらず毎日が目まぐるしく過ぎていく。なんとなく出来上がったグルーブに身を置いて、下手に相手を刺激しないように気を使いながら自分の役割を全うするだけの交友関係。授業は鬼のような速度で進んでいくし、課題の量は膨大、成績は右肩下がり。家に帰れば両親と祖父母の「他より優秀であれ」という無言の圧力が待っている。おまけに鏡に映る自分の容姿はお世辞にも可愛いとは言いがたく、劣等感と無力感が容赦なく思考を埋め尽くす。人より苦労しているわけではないし、何かハンディキャップを抱えているわけでもない。特別誰かと確執があるわけでもない。それでも、どんなに我慢しても頑張っても理想の美しさに手が届かない現状から逃げ出したくてたまらなかった。美しさの欠乏から餓死するのが先か、己の醜さと惨めさにそのまま生き埋めになって窒息死するのが先か。
要するに、今の私は疲れていた。今日は水曜日。嫌な日だ。月曜日と火曜日の分の疲れがたまっているにもかかわらず、週末まではまだまだ遠い。いつになく気分が沈んでいるのは、二日続けて数学の課題のせいで睡眠不足なせいもあるかもしれない。数学に美しさを見出せる人間になれたらどんなに良かったことか。眠い目をこすりながら美術室に入るや否や、ツンとした臭いが鼻をついた。どうやら後輩の女の子たちがネイルアートをやっているらしい。アートはアートなので別に責めるわけではないのだけれど、でれば窓を開けるくらいはして欲しかった。奥の棚から自分のスケッチブックを取り出していつもの一番奥の席に座った。ここ数日、特に描きたいものも思い浮かばず、この席に座ったままぼうっとしているうちに帰る時間になっている気がする。今まで描いていた絵を見返しながらスケッチブックのページをめくっていると、
「なに考えてるの?」
と急に声をかけられた。副顧問である。
「最近ずっとそれぱらぱらしているだけで部活中全然桧描いてないでしょ。スランプかな?」
案外人をよく見ているのだと思った。そんなことはない、と反論したかったが、三十を過ぎている割にどことなく幼さが残る表情で笑いながら言うものだから憎めない。
「しばらく描いてた人形シリーズみたいなのは?もう描かないの?」
「あれは実は今、モデルにしてた子がバラバラになっちゃっていまして」
「パラパラ?」
関節が緩んでいたので一旦すべてのパーツを外して中の紐をしめ直そうと思ったら思いの外難しくって途中で諦めてしまったんです、と説明したら、へえー、と言いつつも困ったように眉をハの字にした。おそらく理解していない。頼りないが、私はこの先生をかなり気に入っていた。なぜなら顔立ちが比較的整っているからである。
「描きたいと思えるものがなかなか見つからなくて。何か良い題材でもあれば良いんですけどね・・・」
「なるほどねぇ。ウゥン、」
この人は歴史の先生だ。彼は美術に詳しいわけではなく、ただの監督者として部室にいるだけなのでアドバイスを求める相手としてはあまり良くなかったかもしれない。顎に手を当てて首をゆっくり傾けるのは彼が真剣な考えごとをしている時の癖だ。なんだか申し訳ない気持ちになってきたその時、
「水族館はどう?」
先生はいかにも名案だろうと言わんばかりに手を軽く叩いた。
「学校の近くのところですか?」
「そうそう。今日の帰りにでも寄ってみたら?お金持ってる?」
「持ってますけど・・・」
正直なところ、あまり好んでいきたいと思う場所ではなかった。行ったところで魚を描く気になれるとも思わない。嬉しそうにしている先生にこんなことを言うのは気が引けたので、
「近くといっても、歩いたら結構かかるし」
と言い訳をしつつ、水族館の案は却下させていただこうと思った。しかし、彼はすぐに納得するかと思いきや、目をさらに嬉しそうに輝かせてこう言ったのだった。
「近道、教えてあげよっか」
私は生涯この先生に感謝し続けるだろう。彼の言葉がなければ、私はあの少女に出会うことすらできていなかったのだから。
*
美術室にいても何もすることがなく時間を持て余していたので、結局先生に言われた通り近道をして水族館に行ってみることにした。水族館の存在は知っていたけれど、実際に訪れるのは初めてだった。外に出ると、もう夕方だというのにあたりは昼間と同じくらい明るかった。あっという間に首筋に汗が滲む。学校の裏に回るとこじんまりとした林があり、その向こうを流れる川に沿って暫く歩くと小さな橋がかかったところを見つけた。橋と言っても、現在は使われていないのか鉄製の柵が置かれて通れなくなっていた。先生曰く、ここが近道らしい。水族館は柵を越えた先にあると言っていた。少々ためらったが、ちょっとした冒険のようで久しぶりの高揚感を感じたので、柵の錠の所に足をかけて一思いに飛び越えてしまった。橋の先にはかなり濃い緑が茂っていて、そこを通る時はほんの少しだけ涼しかった。茂みを抜けると、なるほど確かに目の前に水族館が見えた。入り口まで歩いてカウンターで入場料を支払って館内に入る。蒸し風呂のような外の空気とは打って変わって空調がかなり効いていたので肌寒いくらいだった
私以外に人はほとんどいなかった。矢印が示す通りに魚やエビや貝を順番に見ながら進んだ。絵のインスピレーションはまったく沸いてこなかったが、しっとりとした静けさと揺らめく寒色の照明の空間は疲れた心身を癒して、不思議と落ち着いた気持ちになった。次の展示はクラゲだった。四面の壁の水槽いっぱいにたくさんのクラゲが悠々と漂っている。圧巻の迫カに思わず入り口で足が止まってしまった。どうやらこの水族館はクラゲ の展示に力を入れているらしい。部屋の真ん中にも球体の水槽が設置されていて、その中にも多数のクラゲが漂っている。室内の照明とクラゲが放つぼんやりとした光が非常に幻想的な空間を作り出していた。展示室の真ん中の方まで歩いて行くと、球体の水槽の裏側に珍しく先客がいたことに気がついた。同い年くらいの、見慣れない制服姿の女の子。それが、あの少女だった。
少女はひたすらクラゲを眺めていた。水槽の照明に照らされたその横顔は限りなく無表情で手足には一切の力が入っていないようにさえ感じられた。そして、少女は今まで出会った誰よりも, 何よりも美しかった。丸みのある小さな頭、艶めく色白の肌、整った眉尻、すっきりとした鼻梁、柔らかい目元、上向きのまつげ、薄い唇、細い首、華奢な骨格、夏服から伸びるすらりとした手足。生きた人間にこれほどのまでの造形美を感じる日が来るとは思ってもいなかった。いつも可愛い女の子を見たときに感じる劣等感や嫉妬心や敗北感その他諸々も圧倒的な美しさの前では影を潜めている。目が離せなかった。呼吸を忘れた。足が震えた。
どのくらいの間、私はそうして彼女を凝視していたのだろう。いつの間にか少女の目線がクラゲではなく私に向いていた。私は夢から覚めたような思いで、慌てて息を吸った。
「クラゲを見ていたの?」
少女は不思議な声をしていた。一言一言が耳のうちで何度もこだまして響く、そんな感じがした。柔らかく包み込むような、それでいて鋭く温度の低い声。ただし、一言で表現するとなればやはり美しいという言葉が一番しっくりくる、そんな声だ。
「それとも、私を見ていたの?」
美しい見た目とは裏腹に、少女は意地の悪い質問の仕方をした。あなたに見とれていたんだよ、なんて言える訳がない。すると、少女は狼狽える私を見て、呆れと悲しみの混じった微笑を浮かべた。
「ごめん」
私が謝ると、「なんだ、仲間かと思ったのに」と言って少女は残念でならないという顔をして見せた。
「仲間って?」
「クラゲ仲間」
真顔で突拍子もないことを言う様すら美しい。彼女は疲れ切った自分の脳が見せている幻覚なんじゃないかと疑いたくなるほどだった。しかし、私ではこれほどまでに美しいものを想像することすらままならないだろうから、少女の存在はまぎれもない現実であった。
「クラゲ仲間?」
「クラゲに癒しを求めるの。私はここでクラゲたちに癒されながら考えごとをすることが多いから、あなたもそうじゃないかって期待したんだよ」
どう答えていいかわからなかった。少女の期待に応えられなかったことが、異様なくらい悪いことのように思えた。
「私は美術の題材を探しに来ただけだよ」
「あなたはよくここに来るの?」
「ううん。今日が初めて」
「感想は?」
ああ、私は試されているなと感じた。普段はあまり緊張しないのにこの時は吐きそうなくらい緊張した。自分を見つめる少女の目線が急に恐ろしく感じた。綺麗だ、とか、癒される、とか、落ち着く、という答えでは彼女は満足しないだろう。かといって特に何も、などと言って答えを濁らせればさらに印象が悪くなってしまう。
「美しい空間だなって。どこを見ても美しいから、他の美しくないことをほんの少しだけ忘れられる気がする」
少女の目が興味深そうに丸くなった。とりあえず、少女を失望させることはせずに済んだようでホッとした。別に嘘をついたわけではない。正直な感想だ。ただ、私が意味する美しい空間とは、この美しい少女が佇むクラゲの展示室のことである。もしも彼女に出会っていなければ、ここを美しいと感じるまでには至らなかっただろう。
「あなたはよくここに?」
「私は毎週水曜日にここに来てるの。ほら、水曜日って憂鬱でしょ?疲れも悩みも溜まり始めるのに」
「週末までは時間がありすぎる、そうだよね?」
続きを当てられたのが意外だったようで、少女は驚いた表情をした。そしてすぐに満面の笑みで頷いた。
「うん、そう。だからここでクラゲと気分転換をするの」
規則正しく並んだ小さな歯が眩しい。こんな美しい少女に、一体どんな疲れや悩みが溜まるのだろう。少なくとも他人からの評価や己の美醜にとらわれることはないだろうに。毎週水族館に来られるくらいの時間的余裕や経済的余裕だってあるのだ。
「それじゃ、私はそろそろ帰らなくちゃ。お話できて楽しかった」
少女はそう言って踵を返すと、展示室内を後にした。歩くたびに揺れる長い髪が青い照明を反射して、清らかなきらめきを纏った彼女はまるで異世界の精霊か何かのように見えた。彼女の後ろ姿が見えなくなってからも、私はしばらくその場に立ち尽くしていた。魂が抜けたような気分だった。