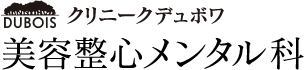『クラゲになりたい』後篇 ―身体醜形症少女の想い
○○高校3年 女子18歳
少女に出会ったあの日以来、私は水曜日が待ち遠しくなった。相変わらず悩みもストレスも尽きないが、絵のスランプは脱出することができた。少女のことを思い浮かべるだけで、描きたい表情や構図が無限に溢れてくる。少女の美しさを完璧に再現するには骨が折れるだろうけれど、何枚も描き続けるうちに少しずつではあるが本人に似てきたような気がする。副顧問も上機嫌だった。少女の存在は私の心の支えになった。
待ちに待った翌週の水曜日、私は学校が終わるとすぐに近道を通って水旗館へ向かった。この日は私が来る時間が早かったらしく、球体の水槽の周りを一回りしても少女の姿は見つからなかった。彼女は私が先にこの場所にいることについてどう思うのだろう。煩わしく思われてしまうだろうか。そう考えると急に不安になり、自分はここに来るべきだったのか、少女が来る前に立ち去るべきなのではないかという焦りを感じた。そこで私は壁の水槽の方のクラゲを眺めていることにした。球体の水槽が彼女の定位置なのだとしたら、そこから少し距離を取っていれば少女の貴重な気分転換を邪魔せずに済むはずだ。壁の水槽にいるクラゲは球体の水槽にいるクラゲよりも少し大きかった。しばらく彼らの動きを観察していると、一定のリズムで傘を開いたり閉じたりしているように見えていたが実はかなり気まぐれであることに気づく。ふわふわと広い水槽の中を漂う様子は大きな変化があるわけではないのに飽きを感じることはなく、むしろどんどん引き込まれていった。半透明な体に少しだけ不透明度の高い触手がついただけの物体。彼らは生命を維持するための働きをする内臓を一体どこに隠しているのだろう。彼らの脳はどこにあるのだろう。何を考えながら泳いでいるのだろう。ひょっとしたら何も考えていないのかもしれない。私にはそのことがとても贅沢なことのように思えた。
「来てたのね」
不意に、少女のあの独特な声が耳元で聞こえた。それはあまりにも唐突で、驚きに心臓が握り潰されるんじゃないかと思った。今日はどうしてそっちの水槽を見ているの、と少女は尋ねた。あなたの大切な時間を邪魔したくなかったから、と言ったら物凄く不満そうな顔をされて、
「私があなたを邪魔だと思うとでも?」
と咎めるような口調で言われてしまった。そういう意味で言ったわけではないのだ、と弁明する間もなく、少女は細長い指で私の手首を掴んで予想をはるかに上回る強引さで私を球体の水槽のところまで引っ張っていった。少女の手が人並みに温かかったことに安堵した。
「クラゲはいいでしょう?あなたの表情を見たら一目瞭然。これであなたもクラゲ仲間ね」
少女は無邪気な喜び方をした。私も思わず笑みがこぼれる。
「どうしてクラゲが好きになったの?」
聞かずにはいられなかった。少女ほどの美しさがあればなんでも似合うと言ってしまえばそれまでなのだが、花や装飾、愛玩動物の方が身近にあって「それっぽい」のに、なぜわざわざ水族館に足を運んでまでクラゲを見るのだろう。すると少女はふと真剣な顔をした。
「クラゲってどうやって呼吸するか知ってる?」
私は首を横に振った。
「クラゲはね、全身で呼吸をするんだよ」
と少女は言った。
「海水を身体中に送ってその中に溶け込んでる酸素を取り込むの。だから彼らには、余計なことを考える脳みそもない。胸の苦しみを訴える心臓もないの」
少女はうっとりとしながら語った。彼女の声が、彼女が紡いだ言葉を私の脳の深いところに丁寧に刻み込んでいく。私も熱に浮かされたような心地がした。
「クラゲは、どんな人が来ても同じように呼吸しながら同じように水の中をゆったり漂っているの。そこが好き」
人間だとそういうわけにもいかないからね、と少女は吐き捨てた。その顔は苦しそうに歪んでいてもなお美しいままだ。私は彼女が理解できなかった。少女の美しさの前には、どんな悪意だって敵いやしない。誰もが屈服し、自ら彼女の足元にひれ伏すことを望むだろう。皆は進んで彼女のために尽くしたいと願うだろう。それなのになぜ、そこまで人間との関係を忌むのだろうか。
「あなたくらいかわいいんだったらみんなよくしてくれるんじゃないの?」
一応疑問形にしてはみたものの、私には確信があった。私だって例外ではない。少女に不快感を抱かせたくないという脅迫めいた感情が働いて、それが彼女の表情の変化に一喜一憂させるのだ。少女が表情をさらに険しくした瞬間、私は己の発言で少女の気分を損ねたことを激しく悔いた。私のあらゆる行動基準である美しさへのこだわりさえ、情けなく揺らぎ始めた。
「だから嫌なのよ」
と少女は言った。やはり理解できなかった。私の怪訝そうな顔つきに少女の目つきが鋭さを帯びる。
「かわいい、綺麗、美しい。そんなの褒め言葉じゃない。同じ人間に、ほとんどは無意識なんだろうけど、上から目線で品定めされてる感じがして大っ嫌い。侮辱もいいとこよ」
彼女は思い切り不快感を露わにした。二人の間の空気が硬くなる。私が少女に嫌われたかもしれないという恐怖に怯えて口をつぐんでいる間も、水槽の中のクラゲたちは相変わらず青い照明を浴びながらのんびりと遊泳していた。
「ねえ、なんで私があなたに声をかけたかわかる?クラゲを見に来たわけじゃないことくらいわざわざ聞かなくてもわかったのに、なんで、私はあえてあなたに声をかけることを選んだと思う?」
目だけでなく、言葉もどんどんもきつくなった。そんなこと私に分かる訳がない。私のほうが聞きたいくらいだ。彼女は私のことを、自分を見つめるただの不審者だと判断して声をかけず足早に展示室を立ち去ることだってできたはずなのに。どうして。少女は私に一体どんな価値を見つけたのだろう。どんな興味を抱いたのだろう。私のどこが彼女の関心を引いたのだろう。
「なんで声をかけられたんだろう、 っていろいろ考えたはずよ。そしていろいろな可能性に期待したでしょう?違う?」
彼女の追求は荒々しかった。研ぎ澄まされた刃物のように私の心の奥へ、奥へと侵入してくる。逃れようとしても、彼女の澄んだ目から逃げることなんて到底出来やしない。
「そこで私が『あなたの顔が好みだったから。それ以上で,それ以下でもない』って答えたら、あなたはどう思う?」
そんなわけがない、という否定よりもまず先に絶望に近い落胆を感じたことに驚いた。私は、こんなに美しい少女に容姿を好ましいと言ってもらっているにもかかわらず、もっと別の何かを望んでいのだ。自分の感情がただただ信じ難かった。
「物足りなさを感じるでしょう?相手に悪意なんてこれっぽっちもない、それでも切なくなるでしょう?」
頷かざるをえなかった。少女はその容姿に好意を示される度に、こんな思いをしてきたということか。だとしたら、私が初めて彼女を見つめていた時も、少女はこうして落胆していたのだろう。私は少女の美しさしか見ていなかったのだから。
「もしこの容姿がなかったら、私は素通りされる程度の存在なのかって勝手に考えて傷ついて、この容姿を失ったら離れられてしまうんじゃないかって一日のうちに何度も何度もどうしようもない不安に駆られるの。だから必死で外面的な美を守ってる。これがあなたに理解できる?」
少女の声は終始静かだった。しかしそこに込められた感情の密度は高く、それらは彼女の瞳、唇、肩を代わる代わる震わせていく。何より意外だったのは、あれほど罵っていた容姿の褒め言葉に彼女がひどく執着しているということだ。溢れるほどの美しさを手にしている少女でさえ、私と同じように美しさにとらわれ、依存しているという事実に寒気がした。
「・・・理解はできる、と思う」
少女と話すうち、私の思考を蝋のように覆っていた美しさへの執着がほぐれ始めたのを感じた。それは嬉しいな、と少女はこわばった表情を解いて笑顔を見せてくれた。
「酷いことを言ってごめんね。さっきのは例え話じゃないの」
少女は申し訳なさそうに微笑んだ。動揺する私を見て、その微笑みが悪戯っぽい笑みに変わる。
こうして話をするうちに、少女はただの美しい存在として眺めているではなく、もっと踏み込んで行きたい、その美しさで霞んでしまっていた少女のその他の性質を知りたいと願うようになっていた。あわよくば、友情を結んで彼女の力になりたいとさえ願った。美しさにとらわれているのは彼女だけではないことを伝えたかった。だからこそ、私は少女に反論した。
「でも、あなたの容姿さえあれば、私の人生は今とは比べ物にならないほど美しくって周りの誰よりも優れていたはず。私がもっと美しければ、ってやり場のない悔しさに何かあるごとに心をかき乱されるの。その気持ちが、美しいあなたに理解できるの?」
今度は少女が口をつぐむ番だった。ゆっくりとまばたきをしながら必死に考えているのがわかる。聡い少女はきっとこの感情の仕組みを理解するだろう。でも彼女は一生こんな感情に苛まれることはないのだ。それだけで、彼女は十分に恵まれているのだということをわかってほしかった。少女が美しさについて気に病むことはないのだ。
「・・・理解はできたわ。でも、あなたは」
「どんなに努力しても手に入らないものを、そうとわかっていながら追いかけるとき、心はどんどん空虚になっていくの。なんで自分はこんなことをしているんだろう、なにも成せないことなんて初めからわかりきっているのに、って。でも何もせずにはいられないから、そういうのを一切合切無視して盲進するうちに、何がなんだかわからなくなるの。これは理解できる?」
つい語調が強くなってしまった。醜い私とは対極にいる存在である美しい少女に、心の内を包み隠さず衝動に任せて吐露するという行為に、恥を感じた。私は少女に軽蔑されるかもしれないと不安になった。
しかし、この問いに対する少女の答えは私の予想とは正反対だった。
「わかるわ。ものすごく」
少女の言葉は力強かった。少女の射抜くような視線が私の瞳を真っ直ぐに捉えた。
「私はずっと探し求めてるから。本当の意味で対等で、純粋な人間関係を」
少女は一言ずつ区切りながらゆっくりと話した。私は彼女の言葉を脳内で反芻した。対等で、純粋な人間関係。そうか、と私は納得した。少女は自分の美しさを対価として支払うことで他人との関係を始めたことしかなかったのだろう。だから彼女は美しくあり続けることでしかその関係を持続させることができないと思いこんでいるのだ。美しさの維持を義務付ける相手の無意識な圧力に気がついたがゆえに、少女はそのことに対して相手との格差を感じ、対等であることを強く望んでいる。だからこそ、互いに互い以外の何も要求しない関係のことを彼女は純粋であると定義し、それを何よりも求めているのだ。私があれほど渇望したものを完璧な形で持ち合わせた少女の苦悩を目の当たりにして、私はいつの間にか己の価値観までをも支配していた美しさへの執着がついに崩れ出していくのを感じた。
「あなたの願いの本質も、ここでしょ?」
やはり少女は聡い。彼女の言葉は正しかった。私が望んでいたのは美しさではない。気配りや親切、成功を常に要求されながら保つ人間関係から解放されたかっただけなのだ。私はこのことをだいぶ長い間見失っていたような気がする。少女の一言で、諸々のわだかまりが全部溶け出していったようだった。
「そうだよ」
「やっぱりね。そのためには何が必要だと思う?」
不思議と答えがわかった。私は、私たちは、たった今対等で純粋な関係を築く最良の相手に出会ったのだから。私たちが目的を果たすために為すべきことはただ一つ。
「私たちの中での、」
口角が自然と上向きの弧を描く。私の唇の動きに、少女の唇が続いた。
「「美しさの概念の破壊」」
少女は満足そうだった。私も満足していた。そしてようやく理解した。少女がクラゲを好み、眺め続けていた訳を。
「だから、クラゲを見ていたんだね」
「そう。こんなにしっかり呼吸をしているのに、彼らには美しさの概念が存在しないからね」
憂の消えた少女の表情は今まで見た中で一番、生き生きとして見えた。少女はただクラゲを求めていたのではない。クラゲは、彼女が捜し求めた理想の相手像であり、また彼女自身の理想像でもあるのだ。私は、少女にとって理想の関係を築ける存在になりたいと強く願った。私にとっても、少女がそんな存在になってくれたらどんなにいいだろうと思った。私はクラゲが羨ましいと思った。クラゲになりたいとまで思った。もちろん少女が美しいからではない。少女を救いたいといというおこがましい思い上がりでもない。理由なんてなかった。
私たちはまたしばらくの間何も言わずにクラゲを見つめていた。少女のほうを振り向くと、まだ美しいと感じてしまった。私が美しさの概念を破壊して、クラゲになるまでは随分と時間がかかりそうだ。それまで、この少女は隣にいてくれるのだろうか。
なんとなく、そんなにうまくはいかないのだろうと思った。そしてこの予感は正しかったのだ。
*
今日は少女がいない七度目の水曜日だ。少女がいなくても、私は毎週水曜日の放課後を水族館で過ごした。年間バスボートを買ったくらいだ。彼女が突然姿を消すまで、十二回会ったにもかかわらず、私たちは互いの連絡先も、通う学校も、名前さえも知ろうとはしなかった。そのことに気がついたのは彼女と会えなくなってからだ。当たり前のように、私はすごく後悔した。せめてなぜ急に来なくなったのか、なぜ事前に伝えてくれなかったのか教えて欲しいと思った。事故か病気か何かだろうか。どこか遠くへ引っ越したのだろうか。彼女の無事を祈りながら、私はクラゲを眺めた。悪い予感からうるさく暴れる心臟も、クラゲの至極ゆっくりとした動きを見ているうちには落ち着いてくる。きっと少女は無事だ、と自分に言い聞かせながら私は彼女が何も言わなかった理由を考えた。何度も考え続けるうちに、なんとなく少女の意図が見えてきた気がした。彼女は私にこの場所に来続けて、クラゲを眺めていて欲しかったのだ。今私がこうしているように、少女の姿があることを期待しながら私がここに通い続けることを、彼女は予想していたのだろう。少女のいない水族館に私が興味を示すかどうか、彼女は私を疑っていたのだ。それを直接言わなかったのは、対等で純粋な関係を望む少女なりの気遣いと後ろめたさから導き出された結論なのかもしれない。あるいは、少女は私たちが会い続けている限り完全な美しさの概念の破壊は為し得ないということを懸念しているのだろうか。
たとえこの水族館でなくても、少女は別の場所でクラゲを眺めているだろうか。一緒に美しさの概念の破壊を進めているだろうか。私は、彼女のクラゲになれるだろうか。願わくは、またあの少女の隣でクラゲを眺めて、いずれは私の成長と感謝を伝えたいものだ。
【自作紹介】
ある真夏の放課後、二人の少女が水族館で出会う。正反対の悩みを抱えながらも同じものを求める二人は、クラゲ展示の前で会話を重ねながら互いへの理解を深めていく。時が経っても薄れず、寧ろ鮮やかさを増していく思い出としてその後の少女たちの記憶にとどまり続けるような、幻想的な物語が書きたかった。