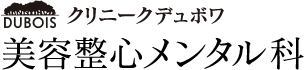不登校
不登校の歴史
第一世代の不登校
1960年代の初めに、「病気でもないのに、家庭環境も良く、学校でいじめとか人間関係でいやなことがある訳でもなく、勉強も好きで、成績もよく、本人も学校は楽しく好きで行きたいと言っているのに、でも朝になるとなぜかどうしても行けない」という子供たちが現れてきた。このような不思議な欠席現象は、一足早く欧米で見出され、1941年に、米国の研究者ジョンソンによって「学校恐怖症school phobia」と名づけら報告された。恐怖症とは、特定の事物や状況に対して合理性を欠いた極端な恐怖心に囚われる心理現象を言い、不登校の子供たちが校門の前で立ちすくんでしまい、パニックになり動けない状況から、学校への合理性を欠いた極端な恐怖反応とみて、高所恐怖症と同じく恐怖症の一種と考えたのである。
我が国でも、この様な理解困難な「欠席」の形が出現すると、精神医学に答えが求められ、そこで精神医学からは「諸疾患のための就学不能、親の無理解や貧困による不就学、非行などが原因となっている怠学などを除外したものを一括して不登校non-attendance at schoolと称する」と定義されたのである。
ここでは病気が原因であるものは除外されるので、不登校はいわゆる病気ではない扱いにはなったが、児童精神医学の中心的なテーマになっていった。
その後ジョンソンは研究を進め、これらの子供たちに共通する心理背景になっているのが、養育者(親)から離れて過ごさねばならない状況への強い不安であることを発見し、この不安を幼児期の分離個体化を持ち越した「分離不安」と名づけた。これは、子供から見れば親への過依存、親から見れば過保護によって生じるもので、実は恐怖症で「学校に行けない」のではなく、不安で「家から離れられないための登校拒否school refusal 」であるとしたのである。
しかし拒否には自分の意志で積極的に拒むという意味合いがあり、行きたくともいけないという実体とはぴったりしないという違和感が残り、またrefusalの意味は、「立ちすくんでしまい動けない」、というものであり、語源的にも拒否は合わないことから、「登校すくみ」などの用語が登場したが、やがて「不登校」non-attendance at schoolという呼び名が定着して行った。この考えは、日本でも支持され、「学校恐怖症」は「登校拒否」と呼ばれるようになり、やがて「不登校」という呼び名が定着して行った。
この新しい形の長期欠席は、頭痛、腹痛などの身体症状から休み始めるケースが多かったので、専門家(児童精神科医)たちは、不登校の身体症状を神経症(今でいう転換性障害、身体表現性障害)として扱うことで解決しようとした。つまり、頭痛や腹痛は心理社会的なストレスがもたらすものとする神経症のせいであり、本人や家族や学校の責任ではないと説明し、「まずは学校を休ませ、メンタルケアをはかることが大切」と説いた。この趣旨から不登校には、対人恐怖や強迫神経症などの他に「神経症的登校拒否」の呼称が診断書に使われたのである。
第二世代の不登校
やがて、1975年以降、年齢や生活環境、文化環境を超えてあらゆる階層の児童生徒に不登校が急激に増加するようになったが、どのパターンにも、共通する現象が見られた。Ⅰ)朝に頭痛、腹痛などがあるが、夕方には元気になる、2)朝寝坊からだんだん昼夜逆転になる、3)断続的な欠席から完全な欠席へ移行する、4)学習意欲はあり、成績は良い場合が多い、5)登校したい気持ちはあるが、できない、などである。急増した要因は、今までの第一世代の不登校にあてはまらない不登校が急増したと考える以外説明のつかないものであった。
現在では幼稚園の登園拒否に始まって、長じては会社への出社拒否すら見られる状況であり、70年代後半の不登校の増加をグラフで見ると、60年代までの典型的な不登校の山がますます高くなる形で進んだのではなく、むしろ典型的な山が崩れて裾野が広がり怠学などの山とも繋がり全体の傘が増えたような形となって増えている。そして文部省は1994年に「登校拒否・不登校はどの児童生徒にも起こりうるもの』と認識するに至ったのである。
80年代に入り、不登校の高齢化が進むと、不登校は、個人と家庭の問題ではなく青少年をとりまく社会的背景、その構造の変化による現代社会の病理現象の一つの現れとして社会問題として捉えるようになった。そこでは、「病んでいるのは不登校になった子供ではない。不登校を生み出した社会であり学校教育なのだ」という主張が生まれ、不登校は「病気」ではないというキャンペーンが起きた。
そして第二世代の不登校は、大きく3種類に分類されて考えらえている。
Ⅰ)学校に行きたい気持ちはあるが、いざとなると不安になって行けないもの、―行きたいのに行けないもの
2)なんらかの理由をあげて登校に関して拒否的な気持ちを持続しているものー行きたくないから行けないもの
3)理由もなく、何となく学校に行かず、学校に関心を失って脱落してしまうものー何となく行けないもの
である。
定義
第一世代の不登校
学校恐怖症
1960年代の初めに、「病気でもなく,利発でまじめで礼儀正しく、身なりも上品で、家庭環境も良く、学校でいじめとか人間関係でいやなことがある訳でもなく、勉強も好きで、成績もよく、本人も学校は楽しく好きで行きたいと言っているのに、でも朝になるとなぜかどうしても行けない」という子供たちが現れてきた。この現象は、従来の経験や考え方では説明がつかず、この様な理解困難な「欠席」の形が出現すると精神医学に答えが求められ、そこで精神医学から「諸疾患のための就学不能、親の無理解や貧困による不就学、非行などが原因となっている怠学などを除外したものを一括して不登校(non-attendance at school)と称する。)(清水将之、1968)と定義されたのである。
ここでは、病気が原因であるものは除外されるので、不登校は本来的には病気ではないことになるが、本人や周りがそれに悩み葛藤が生じ生活に支障が出るので、不登校はいわゆる病気ではないかもしれないが、児童精神医学の中心的なテーマになっていったのである。
このような不思議な欠席現象は、一足早く欧米で見出され、1941年に、米国の研究者ジョンソンによって「学校恐怖症school phobia」と名づけら報告された。恐怖症とは、特定の事物や状況に対して合理性を欠いた極端な恐怖心に囚われる心理現象を言い、不登校の子供たちが校門の前で立ちすくんでしまい、パニックになり動けない状況から、学校への合理性を欠いた極端な恐怖反応とみて.高所恐怖症と同じく「恐怖症の一種と考えたのである。
神経症的登校拒否
しかしその後ジョンソンは研究を進め、養育者(親)から離れて過ごさねばならない状況への強い不安が、これらの子供たちに共通する心理背景になっていることを発見し、この不安を「分離不安」と名付けた。分離不安は、発達心理学でいう分離個体化の過程(2~3歳)の心理の概念であるが、これをこの年齢に持ち越したもので、子供から見れば親への過依存、親から見れば過保護によって生じるもので、実は恐怖症ではなく、分離不安のために登校不能になるのではないかと推察した。「学校に行けない」のではなく、「家から離れられない」という訳である。
この考えは、日本でも支持され、「学校恐怖症」は「登校拒否school refusal 」と呼ばれるようになっていったのである。
しかし拒否には自分の意志で積極的に拒むという意味合いがあり、行きたくともいけないという実体とはぴったりしないという違和感が残り、またrefusalの意味は、「立ちすくんでしまい動けない」、というものであり、語源的にも拒否は合わないことから、「登校すくみ」などの用語が登場したが、やがて「不登校」という呼び名が定着して行った。
この新しい形の長期欠席は、頭痛、腹痛などの身体症状から休み始めるケースが多く、病院に行っても異常がなく、仮病による「怠け休み」と疑われることも少なくなかった。
そこで、専門家(児童精神科医)たちは、登校拒否(不登校)の身体症状を仮病ではなく病気として扱う必要性が生じ、それを神経症として扱うことで解決しようとした。つまり、頭痛や腹痛は心理社会的なストレスがもたらすものとする神経症(今でいう転換性障害、身体表現性障害)のせいであり、本人や家族や学校の責任ではないと説明し、「まずは学校を休ませ、メンタルケアをはかることが大切」と説いた。この趣旨から不登校には、対人恐怖や強迫神経症などの他に「神経症的登校拒否」の呼称が診断書に使われたのである。
第二世代の不登校
60年代から70年代の半ばまでは不登校の年齢層が広がり、パターンも多様になったが、長期欠席率は下降しており、決して不登校が量的に増えたということではなかった。
学校を休む児童生徒の総数は減り続ける中で、登校拒否は、ごく少数だけに起きる極めて例外的な現象であったのである。
やがて、1975年以降不登校が急激に増加すると、そのパターンにヴァリエーションが出てきた。しかしどのパターンにも、共通する現象があった。Ⅰ>朝に頭痛、腹痛などがあり、夕方は元気。2)だんだん朝寝坊から昼夜逆転、3)断続的から完全な欠席へ、4)学習意欲はあり、成績は良い場合が多い、5)登校はしたいができないというアンビバレント二律相反、などである。それらを念頭に先に説明した清水の定義が出来たのであるが、年齢も地域性も越えて、生活環境、文化環境を超えてあらゆる階層の児童生徒に不登校が広がった。不登校は、そのような共通する特異な現象を持つ児童生徒が1975年頃から急増した要因も考えにくいので、パターンから外れた今までの第一世代の不登校にあてはまらない不登校が急増したと考えるのが妥当と考えられた。現在では幼稚園の登園拒否に始まって、長じては会社への出社拒否すら見られる現状である。70年代後半の不登校の増加は、60年代までの典型的な不登校の山がますます高くなる形で進んだのではなく、むしろ典型的な山が崩れて裾野が広がり怠学などの山とも繋がり全体の傘が増えたような形となって増えた。そして文部省は1994年に「登校拒否はどの児童生徒にも起こりうるもの』と認識するに至った。
不登校の急激な増加と高年齢化が起き、80年代に入ると不登校を社会問題として捉えるようになった。不登校は、個人と家庭の問題ではなく青年をとりまく社会的背景、その構造の変化による現代の社会の病理現象の一つの現れとして捉える必要があると認識されるようになったのである。
そこでは、「病んでいるのは不登校になった子供ではない。不登校を生み出した学校教育なのだ」という主張が生まれ、不登校は「病気」ではないというキャンペーンが起きた。
そして多様化した不登校、いわば第二世代の不登校は、大きく3種類に分類される。
Ⅰ)学校に行きたい気持ちはあるが、いざとなると不安になって行けないもの、2)なんらかの理由をあげて登校に関して拒否的な気持ちを持続しているもの、3)理由もなく、何となく学校に行かず、学校に関心を失って脱落してしまうもの、つまり、行きたいのに行けないもの、行きたくないから行けないもの、何となく行けないものの3つである。
現在の定義
現在の不登校の定義として二人の精神科医の見解をあげると以下のようである。
(門信一郎)
「本人、家庭、学校、地域、社会の各々の要因(登校に関しては不利にな条件)の絡み合いによって、子供が精神的に疲労困憊し、登校することに不安を覚えるが、登校しければならないという義務感のために葛藤状態になり、ついに登校できなくなった状態」とする。
不登校は、初めは頭痛、腹痛、発熱、倦怠感という身体症状で始まることが多いが、医者には病気ではないと言われてしまうが、実際は病気ではないが元気・健康でもない「疲れた」状態と言える。
ここで言う不利な条件とは、本人の問題としては、性格(完全主義、潔癖症、感受性が強く傷つきやすいなどの登校には不利な条件になる性格)、親の側の問題としては、学校へのこだわり、学歴主義、世間体などが、学校側の問題としては、義務教育が文部省の独占企業になっていること、いじめ、などがあげられる。
(滝川一廣)
「不登校、登校拒否とは、子供が登校しない(出来ない)と言う現象と、それにまつわる葛藤状況の総称に過ぎない。発熱、腹痛と同じ症状に過ぎず、虫垂炎というような疾患単位を構成できるようなない現象ではない。」とし、あるいは「学校教育という営みに孕まれる何らかの要素との関連において長期欠席が生じ、そこに悩みや不安、葛藤が生まれているもの」とも定義している。
なぜ不登校になるのか?(成因論)
60年代の第一世代登校拒否―精神医学化の時代、恐怖症から不安神経症、神経症的登校拒否へ
1950年代後半に登場した不可解で不思議な新型の長期欠席は「学校恐怖症」として抽出されたが、その後、養育者との分離不安が原因とする神経症としてみるようになった。
しかし、不登校の成因が、分離不安だけでは、(友達の家に遊びに行く時は平気で)学校に行く時だけ、何故そのような状態になるかの説明がつかなかった。そこで滝川は、学校という所には「聖性」があり、それに対する一種の畏れがあること、また不登校になる子供の特徴として、新しく登場して来た、裕福で知的レベルの高い家庭の繊細な神経のこどもであったことから、当時の一般的な粗野でラフな環境で育だった子供達の作る学校の雰囲気に対する一種のカルチャーショックとも言うべき不安があったこと、で説明しようとした。
これらの1950年代から60年代の初めに出現した小学校低学年の新型の欠席現象として始まった不登校は、第一世代と呼ばれるが、この世代が学齢を上げるにつれ、不登校も小学校高学年、中学生と年齢層が伸びて行った。
高校進学率が上がると高校生のなかにも,退学も出来ずに、「学校に行きたい。なのになぜか行けない。」という葛藤に苦しむ高校生の不登校も現れてきた。このように年齢層が上がると、さすがに「分離不安説」だけでは説明がつかないので、「自己万能感脅威説」「回避反応説」「抑うつ不安説」など諸説が主張されるようになった。
「自己万能感脅威説」では以下のように説明する。
小学校、(中学校)までは普通に学校に行けていたのに、中学校(高校)に入ると突然行けなくなるのは、それまでは何でもよく出来る子として自他ともに認めていたのが、中学(高校)に上がって、課題が難しくなると、頑張っても上手く行かない事のある現実にぶつかるようになる。一般にはこうした体験を通して次第に自分の身の丈を知って、子供から大人へと成長していく。人間には誰しも出来ないこと不得手なことはたくさんあって当然なのだが、「なんでもできること」を自己の支えにしてきた子供にとって『何でもできる』という自己のイメージが脅かされるのに耐えきれず、ついには学校に行けなくなってしまう場合がある。つまり私的自己意識と公的自己意識のギャップ
が埋められず苦しむのである。
(これは身体醜形障害(症)にも見られる、思春期における特徴的なこころのメカニズムである。)
登校拒否を逸脱行動論で見ると、学校も塾もきちんと積極的に行く「良い子」の行動も、不登校という形で常識的社会規範から逸脱している行動も、真逆ではあるが同じ逸脱行動として相対化される。前者は強迫的行動であり、後者は反抗・撤退行動となる。「登校拒否」は一人の子供にとっては、それなりに意味や目的を持った行動であり、その中心になっているのは「思春期反抗」といわれる一過性の行動である。
「登校拒否」を生み出す背景には、基本的対人関係の希薄さに始まり、現代の画一化された育児の商品化と呼ばれる諸現象、高学歴社会という流行に毒され過ぎた結果としての子供の生活への介入、管理、その結果起きてくる窒息状況、人間としての生き方の選択をめぐる狭さと不自由さ、などが挙げられる。さらに追い打ちをかけるように、硬直化した仮面をかぶった様な教師達、校則、密室化した学校生活、偏差値を中心にした選別体制といったもので成り立っている「学校の状況」があり、また一方的、強制的に注入される劣悪な「子供文化」がある。
このような現実の中の、思春期における中間総括が、「異議申立て」としての「登校拒否」ではないかと考えることが出来る。
その他諸説があるが、どれが正しいかというのではなく、不登校にはいろんなバリエ―ションがあり、どの観点から見るかという違いに過ぎないのである。
70年代後半の第二世代―反精神医学化 病気ではない論
60年代から70年代の半ばまでは不登校の年齢層が広がり、パターンも多様になったが、社会全般の長期欠席率は下降しており、決して不登校が量的に増えたということではなかった。
しかし1975年を底にして中学生の長欠率は反転して上昇に向かうようになる。
これまで下がり続けてきた長欠率が何故この時期に上昇に転じたかは、不登校の成因を考える上で重要になる。戦後、エンゲル係数も乳児死亡率も下がり続け、75年を過ぎてもなお下がり続けているから、貧困家庭の増加とか子供の健康環境が悪化したために長欠率の上昇を来たしのではないことは確かである。
詳しくみると、50年代には長欠率は全国より都市部の方が低く、急激に下がっており、これは都市部の方が経済回復や近代化が早く、経済的理由や病気による長欠率が地方に先んじて減少したと考えられる。ところが1967年頃から都市部の長欠率が全国の長欠率を上回るように逆転して行く。地方に多かった長欠率が都市部に多い現象になったということは、長欠率の原因が貧困や前近代性から、むしろ豊かさや近代性から生み出されるものへと質的に転換したということになる。それが第二世代の不登校であり、この不登校は60年代の終わりに都市部で増加が始まり、それが都市部から地方へ広がり全国的な長欠率上昇の原因となったのが70年代の後半であった。
1960年代から1970年代始めまでの不登校は、社会全体として長欠率が減っていく中で、特異な現象として現れ「登校拒否」と呼ばれた第一世代の不登校で、本人のパーソナリティと家族関係や学校状況などの環境的な要因と関係から生じた心理現象、つまり神経症的な躓きとして捉えていた。
また第一世代の不登校は、限られた特徴的な条件を持った子供におきる現象で、輪郭のハッキリした典型パターンを持っていた。すなわち「都会の豊かな文化的水準の高い家庭環境に育ち、親は教育に理解があり、知的で真面目で成績良好で勉強も学校も嫌いではなく、同級生からも好かれ学内の人間関係に問題は見つからないといった背景を持つ小学生に限定される。」ものであり、ごく少数におきる例外的な現象で不思議なこととして注目されたものであった。
しかし1975年頃から従来の不登校の要因では説明のつかない程、不登校が急増した。そして文部省は1994年に「登校拒否はどの児童生徒にも起こりうるもの』と認めるに至った。
何故そのようになったか?
「病んでいるのは、子供ではなく学校のほうだ」
不登校の急激な増加と高年齢化が起き、80年代に入ると不登校を社会問題として捉えるようになった。不登校は、個人と家庭の問題ではなく青年をとりまく社会的背景、その構造の変化による現代の社会の病理現象の一つの現れとして捉える必要があると認識されるようになったのである。
中でも児童精神科医渡辺位の見解は波紋を呼んだのである。
「民主社会にあっては個人の尊厳と自由が保障されることが基本であり、したがって教育もまたその理念に従って行われるべきものであることは言うまでもない。それゆえ、学校教育は制度化されていても、子供にとっては個人として本質的要求に沿って成長・発達が保障される生活の場でなければならない。 しかし高度経済成長政策が推進された時代から、各分野はそれに沿って整備、統合、合理化がなされる中で、学校教育もまたそれに沿った人づくりを目指して改変が余儀なくされた。そして教科内容は知育中心に増量・高度化され、学力が偏重される結果となった。
一方、こうした学校状況にあるにも拘わらず、子供を持つ家族は社会通念化した高学歴志向の潮流に呑み込まれ、(中略)ただひたすら形式的通学・進学に執着し、受験態勢を激化させ、子供を、その一人一人の意思や意欲に拘わらず、あたかもベルトコンベアー上の工業製品のように、何の疑問も持つことなしに、上級学校に追い込んでいるのである。
以上の点から不登校という現象を見ると、自己喪失の危機にさらされる学校状況から自己を防衛するための回避行動であると言えよう、例えそれが無意識な発現であろうとも、早期に危機を感知できる直観力はむしろ高く評価するべきである。」
(渡辺位「不登校」清水将行編[青年期の精神科臨床]金剛出版。1982)
渡辺のこの見解は、不登校は子供のパーソナリティ特徴から来る一種の心理的失調とみる従来の不登校理解を根本から覆すもので、当時は強いインパクトがあった。
つまり、「病んでいるのは不登校になった子どもではない。不登校を生み出した学校教育なのだ」というもので、不登校は「病気」ではないというキャンペーンの始まりになった。
この逆転の発想は、実は当時の精神医学が「反精神医学」を掲げ、精神医療改革の運動が世界的に起きていたことと無縁ではなかった。
レイン、クーパーらは、「人間とは社会的な存在で、人間のこころの働きは個人の脳やこころの中で独立して生起しているのでなく、絶えず個人をとりまく社会的な環境の中に会って、環境とのかかわりによって生起している。従って、社会環境に過大な無理や矛盾があればこころに失調が生じても不思議ではない。ところがこれまでの精神医学は、失調を生み出す社会環境に側には目を向けず、ひたすら個人側の脳やこころの問題(病理)として捉えて、個人に「病気」「障害」のレッテルを張ってきた。精神障害者とされる人たちは社会の孕む矛盾や負荷のしわ寄せをこうむった者で、しかも社会は彼等を「病人」「異常な存在」として差別や排除を行い二重に苦しめてきた。精神医学者は医学や科学の名を借りて、それを許容する役目をはたしてきた。」と主張した。
渡辺の説は、レインらが統合失調症で述べたことの不登校バージョンであり、受験ストレスというレベルではなく社会体制全体の問題として捉えたところにあたらしさがあった。
すなわち「高度経済成長政策が推し進められる社会では、学校は産業のための人づくりの場と化し知育偏重・学力強化に走り、子供達は登校と進学に追い立てられるようになった。学校は本来あるべき子供達が個人としての本質的な要求に沿って成長発達が保障される、社会的な共同体に入る準備のための成長の生活の場としての機能を失ったため、子供達は自己喪失の危機にさらされ、そこから身を守る反応として「不登校」が多発するようになった。だから、この社会状況、教育状況が不登校の元なのだ。」という趣旨で、子供主体の自由教育を主張し、不登校に対しては従来の「登校刺激を避ける」ものから「登校しないもの」へと推し進め、これは、その後のフリースクールの設立に道を開いていった。
教育制度の変遷と学習意欲の変化
また滝川は、わが国特有の学校制度の社会的役割の変遷と、教育目標の変化に児童・生徒たちの学習意欲、モチベ―ションの低下がみられるとした。
つまり、我が国では近代化社会装置として学校制度ははじまったが、学校は人びとにとって「立身」、すなわち生活的ないし文化的な上昇へのかけがいのない門戸の意味を持ち、野口英世や二宮金次郎に代表される成功像を描くことが出来、「此岸から彼岸への貴重な門戸としての一種の聖性・絶対性が賦与されていた。学校は「知」の世界へのアクセスとしての絶対性を持ちえていたので、学校に行くこと自体に意義があり、一部に反抗的な子はいても、学校の権威や勉学の一般的価値は子供にも社会にも疑われることはなかったので、学級の秩序の崩壊は起きなかった。さらに戦後になって新制中学が出来ると「学制」の理念は徹底化され、60年代では長欠率は急減し、我が国が第二次産業に転換すると中卒よりは高卒へと、「夢」を求めて高校進学率は急増した。
進学率のピークを迎えると75年を境目に長欠率は一転して上昇に転じた。そして「不登校」が社会問題として登場した。
高校進学率が90%を超え、誰でもが高校に入れるようになった時点から長欠率は上昇に転じた。誰もが高校に行けるとは限らなかった時には、高校進学は手応えを持つ努力目標、夢に向かう主体的な能動的な動機付けになりえていたのが、誰でも進学できるようになればそれは子供の能動的・主体的な努力目標、夢にならなくなり、何のために学校に行くのか、何の目的で勉強をするのか、勉学に励むモチベーションが下がり長欠率の反転を招いたと思われる。従って高学歴志向や受験競争を不登校増加の原因とするのも一般性をもたないことになる。
明治以降近代化を目指した学校制度は、稀に見る成功と達成を果たしたが故に、やがて学校制度が必然的に内包する矛盾や負荷が露呈し制度失調を来すようになった。
多数の生徒を同じ内容を、同じ進度で教育することは元来無理があったし、人間の作る社会制度には必ずや矛盾や負荷が孕まれ、すべての個人に万事良しという社会制度が不可能なことは人間の心が持つ個体性と共同性との矛盾から当然のことである。従ってすべての社会的なことは折合いのシステムでしかなく、そのシステムが大多数の個人にとって存在意義を持つときはその矛盾や負荷も耐えるに値するものとして個人に受容されねばならないし、その時は矛盾も不可も意識されないものである。学校制度も本来的に矛盾も不可も備えていたが、ニーズの高い時はそれらは表に現れなかったが、本来の目的を達成した時から、制度の矛盾や負荷が失調性を帯びたと言える。
70年代に高度消費社会が実現すると貧しい此岸から豊かな彼岸へと上昇する貴重な門戸としての学校のイメージ、それに賦与された聖性・絶対性が学校から喪失し、同時に学問や教育という「知」の聖性も喪失して行った。大学も偏差値でランク分けされた世俗の場になり、「聖域)ではなくなり、ちゃんと商売になって元が取れる研究だけをすればよいという国立大学の独立法人化がそれを明文化し、更に教養過程の廃止はそれに輪をかけている。文化の奥行きは、一見生産性の無い教養を養う余裕から生まれ、また社会や政治の豊かさは、文化の奥行きの深さに依拠するから、このような教養や基礎学問を軽視する教育行政からは、発展は望めないことに成る。国家は役に立たない学問研究には金は払えないといっているのである。
子供たちの側から見ると、すでに豊かになり、多くのものが所与のものとなった社会では、もう学校で汗して努力しても未来がグレードアップされる可能性はさほど見込めなくなった70年代半ばから長欠率も反転上昇に転じた。超一流大学にでも入れば、可能性はのこっているが、「努力次第で誰でも入れる」とゆかぬことくらいは分かっている。しかも高収入家庭ほど可能性が高い現実も知っている。子供たちも個人レベルで「役に立たない勉強に努力は払えない」と感じており、学問に対する態度は国家と同根である。
学業の吸引力が低下したうえ、個々人の欲求と個人意識が繊細化かつ鋭敏化した現在において、学校の集団性は子供同士に共同性意識を涵養するよりも、対人葛藤や傷つきをもたらす場となり、それに耐えてまで学校に行って得られるものが子供にも見えなくなっているのではないか。学校や勉学に向けて人々を引きつける力、子供に登校を促す力が大きく衰えたのだ。そのためささいな葛藤やストレスでたやすく登校の足が引っ張られ不登校に繋がってしまう。これが現在の不登校の本質である。
能力や関心のあり方も様々な子供たちを、大きな集団にして全員に同じ内容、同じ進度、同じ期限で教えて行くのは非合理な方法であり、ある子供たちのレベルに合わせれば、別の子供たちには難しくついていけず、逆にその子供たちに合わせれば別の子供たちは退屈してしまうなど、これは学校教育の集団性が不可避にもつ矛盾である。人間の認識の歩みや達成レベルは個人差がありペンローズの正規分布が示すように、分布の端の生理的群とそれとは別にそこに上乗せされる病理群がある。生理群は、何らの異質性に基づくものではなく、認識という心の働きが自ずと孕む連続的・相対的な差にすぎない。認識という心の働きには個人差があるため、それを社会的に伸ばそうとする教育という営みを集団授業で推し進めることは必然的に矛盾がある。この矛盾は公教育が始まった時からあったが、当初は、それは「機会均等」「平等」という近代社会の理想であり、その頃は同じ勉強ができるという体験の場の共有に価値があった。
近代国家という、新しい大きな共同性に向かって子供たちを育むにはこの『一緒』という共同体験こそが大事であった。また学校の聖性、絶対性が人々に共有されれば、授業が分かるかどうかは大した問題ではなかった。丁度、お寺が神聖でお経は尊いものと言う信があれば、お経の意味が分からなくともお堂に集まって一緒にお経を聞くだけで十分意味があったようなものであるが、信があればこその話で、心がなくなれば無価値で、無意味なものになる。現在の学校はこの信が共有されなくなった状態である。子供にとって勉学が格別尊いものでなければ、分からなければ単に苦痛としか体験されず、子らが不登校や、教室内での逸脱に繋がっているのである。戦後社会は「子供には無限の可能性があり、正しい教育がなされれば、皆自己実現できるはず」という理想主義的な建て前が、教育システムの矛盾を無いことにしてきた。学校に聖性が残っていて、子供たちがこぞって登校している時は「理想」は理想としての力を持っていたが、70年代後半から80年代にかけて現実と理想の遊離が不登校やいじめという形で顕在化してきた。
認識力の差以外にも子供たちの「個性、個別性」を尊重し、かつ子供たちを平等に扱え、差異をつけるな、」という要求の矛盾もあるし、「全員が分かるゆとり教育を」と「しっかり学力をつける教育を」の要求も矛盾として現れている。これらはシステムとしての矛盾であり、システムを変えない限り解決できないが、システムを根本から変えるのは難しいので、この矛盾の解決が現場の教員に責任が押し付けられている。結局これらの矛盾が「不登校」「いじめ」「学級崩壊」「校内暴力」となっている。
現在の不登校は、どんな負荷要因でも登校を持続する動機や意欲をたやすく損なってしまう程勉学や学校の意義が子ども達の間で薄れているという現象である。負荷要因は何でもありで、昔ならこんなことでは休まなかったのにというようなことから不登校は始まる。
以上は70年代後半から80年代に急激に増えた不登校の原因を学校側にもとめるものであったが、一方で批判の的にされた教育サイドからは、原因を家庭の変化に求める意見が上がったのも当然であろう。これは不登校の原因を何らかのパーソナリティの特徴に求めるジョンソン以来のものではあるが、その特徴像は大きく変わっている。
「一般に登校拒否の児童生徒の性格は、自己決定力が弱く、協調性や融通性に乏しく、神経質である。このような性格は、本人の生得的なものもあるが、家庭における養育態度や親の性格などの要因が大きく影響する。長男長女時代に象徴される子供の数の減少や、生活の合理化によってできた時間のゆとりは、わが子の将来への期待に向けられ、過干渉、過保護と言った養育態度として現れる。また社会情勢の変化は父親像・母親像の変容にもつながり、子供の性格形成上必要な生き方を示すモデルとなりにくい場合も少なくなくなった。いずれにしても判断力・忍耐力・協調性に富んだ児童生徒が育ちにくい土壌が家庭内にあることは確かである。」(愛知県教育委員会『登校拒否児童生徒の指導』1989)
「不登校の児童生徒は、いろいろ考えてしまうたちで、踏ん切りが悪く、器用に周りに合わせたり臨機応変に振る舞うのが苦手で、それでまたあれこれ考えてしまい些細なことまで気になってくるタイプで集団行動や集団の人間関係をこなすのがいかにも不得手で、学校の集団生活につまずいて登校できなくなってしまう、という子供」が増えた。この背景には少子化と豊かさが親たちに時間的・経済的ゆとりを与え過保護、過干渉な子育てとなり、学校生活をこなす社会的な力が身についていない子供達が増えた、とするものであった。
登校拒否の偽精神医学化
一方で、不登校を子供たちの情緒障害、青年期における自我の社会化の失敗が原因とし、父親の役割の喪失、子供の父親同一視の失敗に求める考え(高木隆郎)もあった。
更には戸塚ヨットスクールのような、「強い父親の喪失が過度の安逸による脳内麻薬物質の低下が耐性を欠如させ情緒障害の原因となっている」として、暴力を通じて強い父親像を作り上げ、脳幹や脳細胞を強化させるという荒唐無稽な偽精神医学理論も生まれた。
不登校問題が、それだけ解決困難で深刻化していたという事であろう。
なぜ不登校になるのか?(成因論要約)
第一世代の不登校という新しい現象に対しては、学校が怖いという「恐怖症」としての見方から始まり、親・家庭からの分離不安から来る「不安神経症」としての理解、やがて随伴症状の腹痛・頭痛などに注目して「心身症を来たす神経症」としての捉え方がうまれてきた。つまり精神医学の疾患として成因を考えようとしてきたのである。
しかし高校進学率が上がると高校生のなかにも,退学も出来ずに、「学校に行きたい。それなのに、なぜか行けない。」という葛藤に苦しむ高校生の不登校が急増してきた。このように年齢層が上がると、さすがに「分離不安説」だけでは説明がつかないので、「自己万能感脅威説」「回避反応説」「抑うつ不安説」など諸説が主張されるようになった。
「自己万能感脅威説」では以下のように説明する。
小学校(中学校)までは何でもよく出来る子として自他ともに認めていたのが、中学(高校)に上がって、頑張っても上手く行かない事のある現実にぶつかるようになる。人間には誰しも出来ないこと不得手なことはたくさんあって当然なのだが、「なんでもできること」を自己の支えにしてきた子供にとって『何でもできる』という自己のイメージが脅かされるのに耐えきれず、ついには学校に行けなくなってしまう場合がある。つまり私的自己意識と公的自己意識のギャップが埋められず苦しむのである。
(これは身体醜形障害(症)にも見られる、思春期における特徴的なこころのメカニズムである。)
不登校・登校拒否を逸脱行動論で見ると、登校拒否は子供にとっては、それなりに意味や目的を持った行動であり、その中心になっているのは「思春期反抗」といわれる一過性の行動であると理解される。
不登校・登校拒否を生み出す背景には、「育児の商品化と呼ばれる諸現象」、高学歴社会という人間としての生き方の選択を狭める「社会の窒息状況」、偏差値を中心にした選別体制、硬直化した教師・校則・学校生活といったもので成り立っている「学校の状況」があり、またマスメディアから一方的、強制的に注入される劣悪な「子供文化」がある。
このような現実の中の、思春期における子供達の中間総括が、「登校拒否」の形をとった異議申立てとしての思春期反抗ではないかと考えることが出来る。
70年代後半の第二世代
1975年頃から従来の不登校の要因だけでは説明のつかない程、不登校が急増した。何故そのようになったか?を考える中で、「病んでいるのは、子供ではなく学校のほうだ」との説が生まれるようになった。
不登校は、単に個人や家庭の問題ではなく青少年をとりまく社会的背景、その構造の変化による現代社会の病理現象の一つの現れとして捉える必要があると認識されるようになったのである。
すなわち「高度経済成長政策が推し進められる社会では、学校は産業のための人づくりの場と化し知育偏重・学力強化に走り、子供達は登校と進学に追い立てられるようになった。学校は本来あるべき、子供達が個人としての本質的な要求に沿って成長発達が保障される、社会的な共同体に入る準備のための成長の生活の場としての機能を失ったため、子供達は自己喪失の危機にさらされ、そこから身を守る反応として「不登校」が多発するようになったと理解するのである。この社会状況、教育状況が不登校の原因とする趣旨である。
以上の点から不登校という現象を見ると、子供たちが自己喪失の危機にさらされる学校状況から自己を防衛するための回避行動であると言う事も出来る。
この見解は、不登校は子供のパーソナリティ特徴から来る一種の心理的失調とみる従来の不登校理解を根本から覆すものであり、つまり、「病んでいるのは不登校になった子どもではない。不登校を生み出した学校教育であり、社会なのだ」というもので、不登校は「病気」ではないというキャンペーンの始まりになった。
この考えは、子供主体の自由教育を主張し、不登校に対しては従来の「登校刺激を避ける」ものから「登校しないもの」へと推し進め、これは、その後のフリースクールの設立に道を開いていった。
つまり、社会構造と教育制度の変遷と学習意欲の変化が主要因であるとした、不登校は病気ではないとする反精神医学化の動きであった。
一方で、不登校を子供たちの情緒障害、青少年期における自我の社会化の失敗が原因とし、父親の役割の喪失、子供の父親同一視の失敗に求める考えもあった。
また、すべてを母親の問題とする「母原病」説とか、更には戸塚ヨットスクールのような、「強い父親の喪失による過度の安逸が脳内麻薬物質の低下を招き、耐性を欠如させ情緒障害の原因となっている」として、暴力を通じて強い父親像を作り上げ、脳幹や脳細胞を+強化させるという「しごき理論」など荒唐無稽な偽精神医学理論も生まれた。しかしそれらは人権問題から排斥されて行った。
成因論はまさに百花繚乱であったが、それはそれだけ不登校問題が、解決困難で深刻化していたという事を意味するのであろう。
マクロ精神医学の視点で不登校を見ると
不登校問題を、ある断面、ある一方向から見ていてもその問題の本質をつかむことにはならない、それが不登校の問題の解決を難しくしている、というマクロ精神医学的な考え方がある。(滝川一廣)
不登校をどう理解し、対処すべきかは多数の説があるが、結局多種多様、千差万別の不登校現象のうち、その研究者・論者がどのような事例を頭においているかによって生じる差でしかないことが分かる。論争点は①子ども自身の何らかの問題性、②家族関係や養育姿勢の問題,③学校教育の問題性、のいずれかに帰して説明されていたが、実際には、もっと複雑で、これらの3つに帰すことは出来ない。
<何故学校に行けないのか?><なぜリンゴは木から落ちるのか?>に例えて考えてみると、本質論が抜けていることが分かる。
<なぜ学校に行けないのか?>を<なぜリンゴは木から落ちるのか?>で考える
その答えは以下のようになる。
A:林檎の実、あるいは木事態に成因を求める説明法(内在因論)
熟して重くなった,実が腐った、へたが弱った、枝が枯れた
B:林檎がおかれた環境に成因を求める説明法(外在因論)
風が吹いたから、カラスがツツイタから、人が木を揺さぶったから、害虫が付いたから
C:諸要因の複合と説明する説法(複合成因論)
熟して重くなった実は落ちやすい上、熟したリンゴは食欲をそそるので、カラスがツツイヘタが弱くなり僅かな力でも枝を離れやすい。これらが複合してリンゴは落下する。
D:一概に何が成因とは言えないとする説明法(ケースバイケース論)
カラスではなく雀の場合もあろう̪、自然落下する例もあり、成因は一概にいうべきではない。林檎落下は症候群に過ぎない。
いずれも間違ってはいないが、問に対して本質論にはなっていない。本質論はニュートンの重力論である。
不登校の、(あるいは精神医学一般の)成因論も、このAからDを乗り超えていないようだ。
不登校成因論の定型を対比してみると、
A.内在因論
子供ないし家庭の在り方に本質的要因を求めるもの。
サンプルA:登校拒否の児童生徒は、自己決定力が弱く、協調性や融通性に乏しく、神経質である。このような性格は生得的なものもあるが、家庭における養育態度や親の性格などの要因が大きく影響する。少子化や社会情勢の変化は親が子供のモデルになりにくい状況を作り、判断力・忍耐力。協調性に富んだ児童生徒が育ちにくい土壌があることは確かである。
B.外在因論
「学校環境」ないし、社会全体の教育環境の在り方に本質的要因を求めるもの。
サンプルB:学校教育は知育に偏り、内容の増量、高度化から能率一辺倒になり画一化が起こり、学校現場も多彩多様な子供一人ひとりに柔軟に対応することが困難になった。結果子供たちに大きな精神的負担がかかるようになった。さらに最近の学歴偏重、高学歴志向は受験競争を激化させ、知育編重となりよりストレスへと追い込むものになった。
C.複合成因論
ABのブレンドしたものー折衷説である。
D.ケースバイケース論
問題が複雑であると言っているだけ。複雑多岐な現象から普遍的な認識を引き出す努力を放棄しているともいえる。
つまるところ、不登校の成因論はA,Bの2パターンに集約される。
Aは「要するに近頃のリンゴはヘタがひ弱になったからだ」とするもので、Bは「いや、要するに風が強いくなってきたからだ」とする議論である。
リンゴ落下の成因論において「熟したから」「腐ったから」「風が吹いたから」「カラスがつついたから」と並べられるように、すなわち、分離不安が強かったから、社会性が未熟だった、自我が弱かった、家族内に葛藤状況があった、学校教育が画一的になったから、受験体制や管理が強化されたから、などがこれまでの不登校の成因論であるが、結局これらの各説は、「こういう場合に林檎が落ちる」「いや、こんな落ち方もある」「私の観察した林檎はこんな落ち方をした」「近頃は、こんな風な落ち方も見られる」と、各人各様に取り出してきたものに過ぎない。
仮に引力が強まれば、今まで落ちなかった林檎も落ちるようになるが、その引力に相当するもの(引力が無ければ林檎は落ちない)、すなわち社会全体の中で子供たちを不登校にしやすくしているマクロな本質要因、全体を貫く大局的な事象が何かという視点が重要であるが、その視点に欠けた論説が多いのである。
サンプルAもBもそれが当てはまる子はいて、そこに限っては自己完結的に概念を作りあげることは出来るが、同じ状況でも不登校にならない子もいるし、そのような理由がなくとも不登校になる子もいる。
滝川は、リンゴが落ちるのは、どんな落ち方にしろ、重力が根本的な共通原理であり、このようなマクロ的な視点無くして心の本質に迫れないだろうという。たしかに重力が無ければリンゴは落ちないが、しかしたとえ重力が存在しても、同じ重力下で、落ちる林檎と落ちない林檎のある理由の説明は出来ないであろう。しかし重力の存在を無視して、落ちる理由をあれこれ言ってみたところで始まらないのも事実である。
滝川は統合失調症、双極性障害、自閉症、不登校という従来の精神病理学では病因の共通原理を見出し得なかった精神障害を、共通原理で説明しようとしている。
個人的共同体から社会的共同体への移行に必要な力
人の存在する世界を個人的な関係世界、パーソナルな共同性世界と、個人性を離れた社会的な関係世界、インパーソナルな共同性世界の二つの位相世界に分けて考え、精神の発達を個人的(パーソナル)な共同世界から社会的(インパーソナル)な共同世界への依存の在り方で説明し、それへの依存の関わり様で、統合失調症、双極性障害、自閉症、不登校の病理を説明してみせた。
精神発達とは、認識(理解)と関係性(社会性)の両面で発達するが、一個の個体として生まれ落ちた子供が、養育者への依存に始まって、人々が互いに依存し合う共同性の世界(個人的関係世界から社会的関係世界)に次第に歩み寄っていく過程に他ならない。
依存を本質とする我々にとって、関係における安全や受容や承認のいかんは共同性を生きることに関わる死活問題であり続ける。
人間が生きる関係世界は、大きくとらえれば二つの位相の違う世界からなっている。
一つは個人的な関係世界であり、個人性を備えたある人とある人との関係からなるパーソナルな共同体である。それは吉本隆明が言うところの、性(身体)に媒介された家族的な関係から生まれ、その関係を支える観念、(対幻想)の世界であり、また小浜逸郎が言うエロス的関係に当たる。エロス的関係とは、セクシャルという意味では無く、いわばその人から滲み出る風貌とか表情とか雰囲気とか息使いとか、そういう身体性をはらんだ親和性(エロス性)が関係の成り立ちに深く預かる関係という意味である。
もう一つは、そのような個人性を離れた関係の世界、社会的な関係世界(インパーソナルな共同体)、
であり、すなわち社会的役割を通した関わりの世界、職場のスタッフ同士、顧客と店員など抽象性の高い関係である。これは吉本隆明の言う、共同体的な関係から生まれ、その関係を支える観念である共同体幻想であり、それは身体的媒介を持たない観念、観念的な観念であり、まさに幻想であると言えよう。(そのような観念を必要としなくなるのが人類の遠い課題であるというのが吉本の思想の骨格であろう)小浜逸郎の言う「社会的関係」は、エロス的関係は切り捨てられ、より抽象的でインパーソナルな社会的な役割性が関係をつなぐものとなっている。さらに抽象性が高くなれば、直接の接触の無い「市民」とか「国民」と言った抽象概念によって社会的な関係のネットワークがつくられ、「国家」のような大きな相互依存の共同性を生み出し、そのような社会性の位相で我々は生きていることになる。
ところが、私達はこうした重層的で高度の共同世界を作り上げ、そこで依存し合って初めて生存を可能にしながら、一方ではこうした共同性を不自由なもの、制約的なもの、生きにくいもいのとする違和の意識も持っている。これは、矛盾した非合理な心的作用であるが、この矛盾は私たちが共同的な存在でありつつ、一人一人が個体の存在(孤的存在)であるところからきているのではないかと思われる。
人のこころは、個人の脳に存在していながら、第三者との共同体の中でしか存在しえないという本質的な矛盾に、その原因がある。
人は、発達過程で生まれ育った家庭(パーソナル共同体)から、学校、社会という社会的共同体(インパーソナル共同体)に寄り添い依存する関係性を作っていくが、その際、そこに生得的に持っている共同性の不自由さを不安として感じるが、その程度が自我の強さを上回れば、自我防衛として不登校という形をとると考えることが出来る。パーソナルな共同体からインパーソナルな第三者との共同体に参入するには、それなりの自我の強さがいるのである。
私の自律統合性機能AIF理論での解釈
私の自律統合性機能(AIF)理論(ホームページ『クリニックの理念と自律統合性機能』、著書『ほんとうに美しくなるための医学』アートデイズ出版参照)では、ライフサイクルの要所要所では、特に思春期では第二次性徴期の身体の急速な発達で、身体的には自律神経系、代謝系、免疫系が揺さぶられ身体波が乱れるが、合わせて心の自我機能が不安定になり、身体波、精神波の共振状態が乱れ,自律統合性機能に負荷がかかり、心身共に人生の岐路と言えるほどに不安定になる。
この時に不安定さが失調状態になったのが私の提唱する思春期失調症候群であり、不登校もその一つである。
心・神経系(自律神経)・免疫系・代謝系の4つ機能が上手く協調し自律神経のバランスを復調させることが出来れば、AIF機能は復調し、精神波、身体波のリズムも再び共振を取り戻し健康状態にもどることが出来る、と説明する。この際重要なのは、身体系ではホメオスターシス・恒常性機能であり、精神系ではレジリエンス・抗病力の強さである。
こころの自我機能の弱体化は自律神経系を通じて免疫力を下げ、代謝系ではホルモンバランスを乱し、身体的健康を損なうことになる。逆に言えば、自我機能がしっかりしていれば、自律神経のバランスは保たれ、免疫系、代謝系も正常に機能するので、精神波、身体波の共振が障害されることもなく、心身共に正常な発達をとげることが出来る。
これはアイデンディティの確立を得て社会に上手く適応していくことを良く説明できる。
思春期・青年期の課題として、個人的共同体から社会的共同体への参入するために自我同一性(アイデンディティ)の確立が必要であるが、この時は本来的に個である人間が共同体での協調性に耐えうるだけの揺るぎない自我が形成されていなければならないが、それが未熟だと(多くは、基本的信頼、自律性、有能感が獲得できていない)共同体への参入を回避して、登校拒否、引きこもりになったり、行為障害、自傷、家庭内暴力、醜形障害などとして表出して参加を拒否することになる。
自律神経理論で見ると、交感神経と副交感神経のバランスを崩しやすいのが、ライフサイクルの変換期であり、特に思春期である。
ストレスがかかり、交感神経優位になると身体生理的にはホルモンバランスを失い、白血球の顆粒球が増加、リンパ球が減少し、結果として免疫力が低下し、活性酸素も増加する。心は不安定になり怒り、不安、おびえ、恨み、傲慢、絶望などネガティブな感情に支配される。
このようなときは活性酸素を下げ、免疫力を上げ副交感神経優位にすれば、心の働きは、感謝、喜び、安堵,愛しみ、謙虚さ、希望などのポジティブな感情が強くなる。
思春期、思春期以降の不登校・引きこもりの遠因は、パーソナルな共同体から第三者と交わる社会性を求められるインパーソナルな共同体へ参入する際の不安、戸惑いが大きなストレスになっていることが原因であると私は考えている。
学校はかつてのような家族的なパーソナルな共同体の性格を失ってきているのである。
それに合わせて自我はアイデンディティの確立を必要とされるが、たとえそこまで行かなくとも自己が「個」として確立され自尊心が維持される必要があるが、その瀬戸際に追い込まれると、自我防衛のために逃避したり、防衛的攻撃行動に出てくるのである。それが不登校・引きこもりであったり家庭内暴力や非行など行為障害になるものと思われる。身体醜形障害(症)も逃避のための自己防衛の形と解釈すれば、同根である不登校・ひきこもり、自傷行為、摂食障害引を伴いやすいことの説明もつく。
共同体にありながら個(自我)を守るには、共同体への協調性に耐えるだけの自我の強さが必要で、それがアイデンディティであり、また自我を守れる最後の砦が自尊心ではないかと私は考えている。
治療について
治療論が成因論によって変遷するのは当然で、1960年代までは分離不安説に立脚した鷲見たえ子の説、強迫神経症ないしは対人恐怖症として位置付けた高木隆郎の説、両親の性格特長の影響、とりわけ父親の役割と母子間の情緒的結合の不十分さに重きを置いた山本由子の説などがあり、これらは不登校を神経症的なつまづきとして精神医学的範疇に収めて理解し、治療しようとするものであり、特徴に応じたカウンセリングを行うものであった。それはそれなりの進歩をもたらしたが、他方では精神医学に納まりきらない要素は抜け落ちてしまう結果になった。
1970年代に入ると,反精神医学化とも言うべきアンチテーゼが提出されると、治療に対する考え方は、強制的処置などによって一方的に登校を督促することは、一層子供を窮状に追い込み、葛藤を強め、自我を萎縮させるのみであるから、単に不登校という状態を現象的に解消し登校状態に矯正・変更するのではなく、第一には子供の心理状態に基づく二次的反応を解除することであり、第二には不登校という学校に対する行き詰りについての問題解決である、ということに変わって行った。二次的反応とは、葛藤によって生じる攻撃や隠遁、腹痛・頭痛といった身体症状、不安神経症、強迫神経症のことを言う。
これはややもすれば、陥りがちな心理主義、家族内力動主義の弊害から子供や親を守る一定の役割を果たした。
このように、時代的には不登校・登校拒否の精神医学化、反精神医学化、偽精神医学化、反偽精神医学化の4極の流れがあった。
現在の治療論では定説は無いが、概況を見ると、「本人の意思を重視するものの、家庭内暴力が始まったり、長期化した場合、あるいは抑うつ症状、不安・強迫症状、社会的回避と言った問題の深刻化が起きた場合は入院医療と勧める」というものが多いようだ。
入院の目的は、1)家族から分離する、2)保護的支持的な枠組みが与えられること、3)心理的成長の場と時間と人間関係が与えられる4)院内学級で授業が受けられる、という利点があるとされ、根拠はパレンス・パトリエ理論にあるが、このような目的がかなう入院施設がはたしてどれだけあるか疑わしいとしている意見もある。
最近の動向として、不登校・登校拒否を不安障害や行為障害といった精神医学的診断範疇にもう一度分解して位置づけようとする考え方が登場してきている。
また一方で、病気ではないが、かといって元気・健康でもない「疲れた」状態が招く登校拒否に対する対策が必要ではないかという考え方も登場してきたが、これはまさしく私の提唱する整心精神医学的な理解である。
それには子供の「休む権利」を認め、いわば年次休暇を与えて、表向きの不登校状態を無くすのが良いとしている。同時に登校に不利になる様々な条件、例えば、1)完璧主義、潔癖症、感受性が強く傷つきやすい本人の性格、2)学校へのこだわり、学歴主義、世間体と言った親の都合、3)義務教育が文部省の独占企業になり、支配されていると言った学校側の事情などの改善を図っていくことが必要であるとしている。
つまりは本来的な不登校・登校拒否を「疲労としての登校拒否」として捉え、それに対しては徹頭徹尾、休む権利を与え、それを保証することであり、それが治療の大原則になるとしているのである。そして周囲は干渉せず、いつか本人が社会に参加しようとした動きが出た時にリハビリテーションの場を用意することであり、現在では思春期デイケア、フリースクール、大検予備校などの社会資源があると述べている。
また狭義の精神疾患と診断される登校拒否については、強迫神経症、抑うつ状態、統合失調症、パーソナリティ障害、高機能自閉症など発達障害の鑑別診断をし、その原疾患の治療を行うことになる。大事なのは、これらの病名が診断されても、それで学校との関連性を断たないことで、社会復帰のために学校と関係を継続しておくことが重要であるとしている。
「思春期失調症候群」としての視点から
以上、その始まりから現在までの不登校・登校拒否の意味、定義の変遷から、その成因論と治療論を見てきたが、それらは不登校を単独な一つの症状として捉え、考えるものであった。
不登校の中でも症例も多く深刻なものは、狭義の精神障害に伴うものではなく、中学・高校に始まる、いわゆる思春期の不登校・登校拒否で、それらは家庭内暴力、自傷・リストカット、摂食障害、行為障害、身体醜形障害(症)、境界性パーソナリティ障害などを併発し、生活が社会的に機能せず、やがて長期に渡って引きこもりに至ってしまうものではないかと思う。
私は、不登校は思春期という人生の過渡期の発達段階・ライフサイクルの危機的課題・ハードルを上手く越えられずに躓いた時に生じる様々な症状(パーソナリティ障害、摂食障害、自傷症候群、行為障害、身体醜形障害(症))の一つとして捉え、それらに共通する分母となるもの、つまりリンゴが落ちるのは、色んな事情があろうとも、基本的には重力があるからだとするような、マクロな視点で不登校の成因を考えれば、また違った視点で本質的な治療論を考えることが出来るのではないかと考えている。
不登校に対して、ここで記載したような先人たちの考察に加え、思春期失調症候群としての視点からも捉え、自律統合性主義をベースに置いた独自の心理精神療法としてマインドフルネスレジリエンス療法とレジリエント生活・食事療法を行って対処していくのが有効であると考えている。
参考図書
1)川合洋「学校に背を、向ける子どもたち」MNKブックス、1988
2)門慎一郎、高岡健、滝川一廣「不登校を解く」ミネルヴァ書房、1998
3)滝川一廣「なぜ、人は学校に行くのか?「不登校」理解、ここから始まる!」日本図書センター、2012
4)高木俊介「ひきこもり」MHL、2002
5)稲村弘「不登校の研究」新曜社、1994