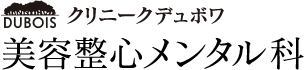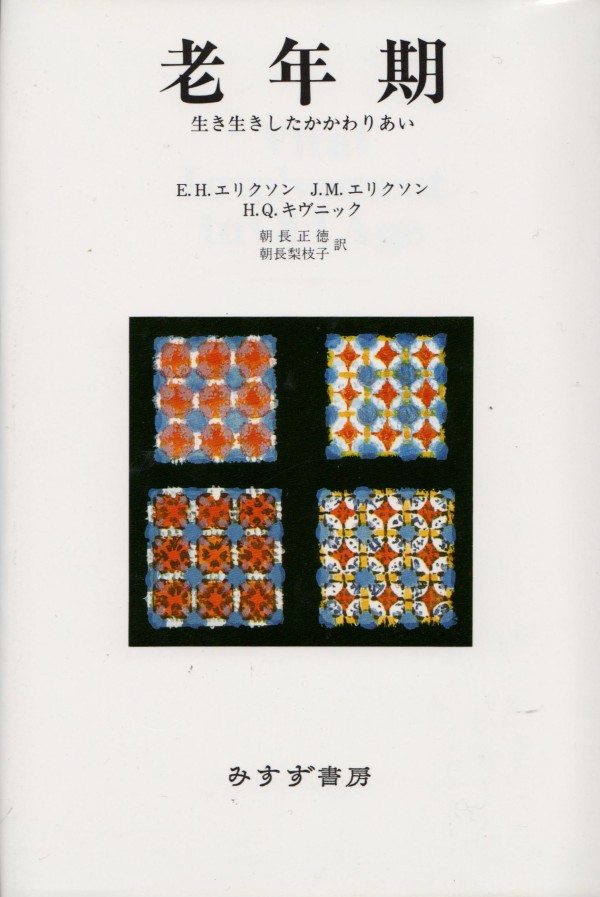エリクソンのライフサイクル⑦ Ⅷ期・老年期(56歳から)-「統合性/絶望」-人は最後に人生への感謝を問われる
エリクソンの8つのライフサイクルの8番目が老年期である。老年期は人生の終盤、晩年の時期をいうが、成人期が55歳までであるから56歳からが老年期になる勘定であるが、現代では平均寿命も長くなり、50代は成人期とあまり変わらないので、56差から65歳までを向老期とする考えもあり(神谷美恵子)、一般に受け入れられているようである。
またエリクソンは晩年には、80歳以上を9番目のサイクルとして分けた方が合理的であるとしている。
人は常に老いを自分とは関係のない異質なものとして否認しつつ生きているから、老いを自覚するのは突然、ふっとした出会いによることが多い。成人・壮年期に心身の若さが下降局面に入ったと思った時に老いることの予期不安を覚えるが、向老期には老いることが確信に変わり、老年期には老いが現実のものとなる。
老いを受容するのは難しいが、それでも老いは緩やかに確実にやって来る。まずは心身機能の低下、老化の兆候が出てくる。それは死の自覚である。
社会的には、定年、退職など青年期から壮年期に努力して築いた自己の生活基盤、自己のあり場所としていた仕事から去ることを意味する。家庭内での立場も変わり、孤独感と無用者意識が発生する。
無用者になることの方が定年退職よりもっと耐え難いことである。それは経済的な問題もさることながら、心理的に社会からスクラップのように投げ出されてしまったと感じるからである。
向老期は、普通は未だ真の無用者ではない筈であるが、少なくとも覚悟はして、この新しい自己像を受け入れることがこの時期の困難な課題であり、第二の思春期と呼ばれる所以であろう、私はこの時期を「思秋期」と呼ぶのが相応しいような気がしている。
思春期が人生の旅立ちにあたって自己像を受け入れていくのに対し、思秋期が旅の終わりに当って新しい自己像を受け入れていくのである。
この受け入れにあたってのエリクソンの心理社会的危機の課題は「統合性(完全性)」で表現される。
エリクソンの「老いつつある人」の中で考えを見ると、
「ものごとや人間の世話をしてきた人、他の人間を生み出したり、ものや考えを作り出し、それに伴う勝利や失望に自らを適応させてきた人―そういう人においてのみ、これまでの七段階の実が次第に熟して行く。この事を言い表すのに統合integrity以上にいい言葉を私は知らない。それは自分の唯一の人生周期ライフサイクルを代替不能なものとして、まさにそうあるべきものであったとして 受け入れることを意味する。なぜならば一人の個人の一生は単なる一つのライフサイクルが歴史の一コマと偶然にぶつかったものに過ぎないことを、こういう人はよく知っているからである。」
このように「老いつつある自分」を全体的に受容出来た人には、「英知」「知恵」という徳または力が現れるとエリクソンは言う。
「英知」とはすなわち死に直面しても人生そのものに対して「執着の無い関心」を持つことである、これの備わった人間は心身の衰えに拘わらず、自己の経験の統合を保ち続け、後から来る世代の欲求に応えてこれを伝えるが、しかも「あらゆる知識の相対性」を意識し続けている。-もし、知的能力と共に責任を持って諦める能力を併せ持つならば、老人達のうちには、人間の諸問題を全体的に眺めることが出来る人がある。これこそがintegrityの意味するところである。「このような自我の統合」に達することが出来なかった老人は、もはや人生のやり直しがきかないという「絶望感」を持ち、人間嫌いになったり、絶えず自己嫌悪に陥ったりすることが臨床的に観察されるとエリクソンは加えている。
これについて、神谷美恵子は次のように解説している。
「成人は自分の生み出したものに対して責任を取り、これを育て、守り、維持し、そしてやがてはこれを超克しなければならない。」つまり、老年になってからは、自分が一生の間に「世話をし」、守り育ててきたものを相対化し、客観化しなければ「人間の諸問題を全体的に眺める」ような「統合」に達することが出来ない、というのがエリクソンの考え方なのだ。一生をかけた事業、学問があれば執着も大きいだろうが、自分の過去についての見方も、突き放して見る習慣を養っておかねば心の安らぎは得られないだろう。自分の過去についてこそ、エポケー判断停止が必要とされている。
つまりどのような仕事、学問、業績を生きがいにしてきたにせよ、すべては時と共にその様相も意義も変わっていくものだ、自分の後から来る世代によってすべてが引き継がれ、乗り越えられ、変貌させられて行く。その変貌の方向も必ずしも進歩とは限らない。分散か統合か、改善か変革か廃絶か、歴史の動向と人類の未来は誰が予見できようか。自分の過去の歩みの意味も自分はもとより、他人にもどうしてはっきりとわかることがあろう。その時その時精一杯に生きてきたのなら、自分の一生の意味の判断は、人間より大きなものの手に委ねよう。こういう広やかな気持ちになれば自分の過去を意味づけようとして、やきもきすることも必要でなくなる。徒に過去を振り返るよりは、現在周りにいる若い人たちの人生に対して、エリクソンの言うような「執着の無い関心」を持つ事も出来よう。彼らの参考になるものが自分にまだあるなら、喜んで提供するが、彼らの自主性をなるべく尊重し、自分は自分で、命のある限り、自分に出来ること、なすべきことを新しい生き方の中でやっていこう、という境地になるだろう。
自分の人生を振り返り満足できると危機感を感じないで幸福に人生を終えることができるといい、すなわちそれが統合、完成であるが、それには宇宙という大きな秩序の中で自分を捉えることで達成されるとエリクソンは言う。
健康に幸福に生きてきた人の心は、そういう満足と感謝の境地にいたるもので、死んでも死にきれないという人や、未だ人生に感謝できないと言う人は、きちんと老年期を迎えていないのだ、という。最後に問われるのは、「人生に感謝できるか」が課題となる。感謝できる人は危機感を持たずに死んでいける。感謝出来る人は年を取ることを受け入れることが出来る。
この宇宙観に通じる、神谷美恵子の素晴しい文章があるので最後にそれを紹介する。
老いて引退した人間の最大の問題の一つは、社会的時間の枠が次第に外されていくところにある。体内時計の回転は遅くなっていくうえ、周りからの押し付けられる時間の圧力が減ってくると、うまく時間を自主的に支配するのが難しくなってくる。このことを良く覚悟したうえで、自主的に自分なりのペースで生きる時間の用いかた、配分の仕方を考え、超時間的に時間を観ずることが出来るようになるのが望ましい。そうすれば自分の一生の時間も、悠久たる永遠の時間から切り取られた極小さな一部分にすぎないことがわかるであろう。
自分は自ら志願してこの世に生まれてきたわけではない、この永遠の時間の一部分を意識して生きる人間存在になろうと願い出てきたわけでは無かった。しかし生まれたからには与えられた時間を精一杯生きてきた、時間を充実させて、なるべく良く生きようとは努めてきた。しかし、自分の一生には多くの若気の至りや過ちや「もっと良く出来たはず」のこともあるだろう。他人が自分をどう見るかは大した問題ではない、その他人もまた死んで行くのだから。
それより自分こそ、自分の一生が完全無欠なものでは無いことを知っている。ましてや、もっと大きな目から見れば、自分の一生などなんとおかしな、滑稽な憐れむべきものであろう。それにもかかわらず今まで人間として生きることが許され、多くの力や人によって生かされてきた。生きる苦しみもあったが、また美しい自然や優れた人に出会う喜びも味わえた。そしてこれからも死ぬ時まで許され、支えられて行くのだろう。これからも自分が意識するとしないとにかかわらず支えられて行くのだろう。永遠の時間は自分の生まれる前にもあったように自分が死んだ後にもあるのだろう。人類が死に絶えても、地球がなくなっても、この「宇宙的時間」は続くのだろう。自分は元々その宇宙的時間に属していたのだ。だからその時間は自分の生きている間も自分の存在を貫き、これに浸透していたのだ。
時間を一つの流れに例えるのなら、岸辺に在ってその流れを見ている観察者を想定しなければ成り立たない比喩だという意味のことをメルロー・ポンティは言ったが、厳密な意味では人間はその観察者たりえない。人間は流れそのものの一部なのだから。誰かが観察しているとすれば、それは「神」か何らかの超越者だろう。
私は神谷の言う超越的存在は、何も形を持った有機体を想像しなくても良いのではないかと考えている。それが、私が自律統合性機能autonomous integrity funcionと呼ぶような超越的な宇宙統制システムであるとすると、神ではなく私の宇宙観でも良く説明できる。